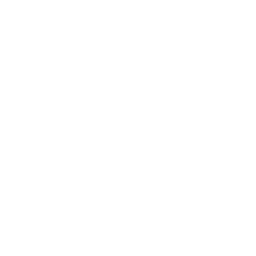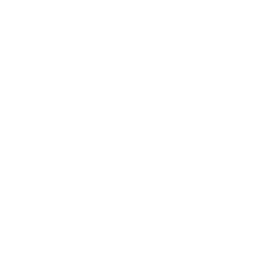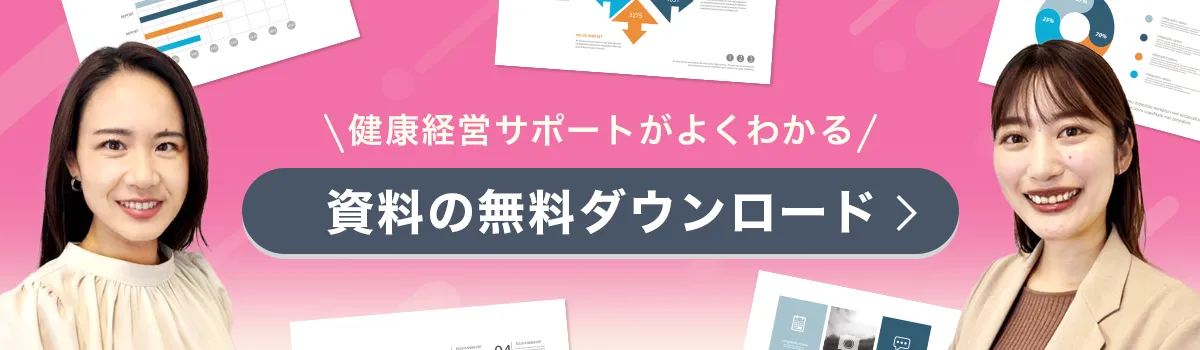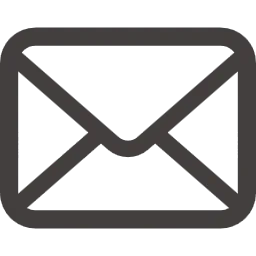厚生労働省が推進!コラボヘルスの基本と導入ステップ

コラボヘルスとは、厚生労働省が推進する健康保険組合と企業との連携により、組合員の健康保持増進を目指す取り組みです。この連携を通じて、健康データの共有や分析を行い、より効果的な健康サポートを提供することが可能となります。
この記事ではコラボヘルスの定義と目的を明確に説明し、企業と健康保険組合がどのように連携し、仕組みを構築しているかについて具体例を用いて解説します。
コラボヘルスとは?基本概念の解説
コラボヘルスとは?
コラボヘルスとは、健康保険組合(保険者)と企業(事業主)が連携して、従業員やその家族の健康づくりを支援する取り組みです。具体的には、以下のような活動を含みます。
・健康増進:従業員の健康を維持・向上させるためのプログラムや活動を実施します。
・労働災害防止:安全な職場環境を整備し、労働災害を防止します。
・データヘルス:健康診断や医療データを活用して、個別の健康指導や予防対策を行います。
・健康経営:従業員の健康を企業の重要な資産と捉え、健康増進に向けた投資を行います。
これにより、従業員の健康が向上し、生産性の向上や医療費の削減が期待されます。
健康経営との関連性

コラボヘルスは、企業と健康保険組合が連携し、従業員の健康データを共有・分析することで、健康増進や疾病予防をし、健康経営の推進に寄与します。
健康経営とは、企業が従業員の健康管理に積極的に取り組むことで、従業員の生産性向上や企業の持続的成長を実現する経営手法を指します。コラボヘルスとの関連性において、健康経営は単独ではなく、健康保険組合や企業との連携を通じてより効果的な施策が実現されます。
これにより、個々の組合員に最適化された健康支援が可能となり、企業の健康経営戦略を強化します。また、双方の連携が相互に補完し合い、シナジー効果を生み出すことで、より効果的な健康管理体制の構築が期待されます。
保険者と企業の役割分担

健康保険組合(保険者)の役割として、主に健康データの収集・分析や健康増進施策の企画・実施が挙げられます。具体的には、以下のような内容です。
・加入者の健康状態を把握するためのデータヘルス活用
・予防プログラムの提供
・健康教育の実施
これにより、組合員の健康維持・向上を支援し、医療費の抑制にも寄与します。
一方企業側の役割では、職場環境の整備や従業員の健康管理に直接関与する活動が求められます。具体的には、以下のような内容です。
・健康診断の実施
・ストレス管理プログラムの導入
・フィットネス施設の提供
・従業員の健康意識を高めるための社内イベントやセミナーの開催
保険者と企業の協力体制においては、双方の強みを活かしながら効果的な健康増進施策を展開することが成功の鍵となります。例えば、ある健康保険組合では、企業と連携して定期的な健康セミナーを開催し、組合員の健康意識向上に成功しています。
LAVAの法人会員サービスで従業員の健康管理!詳しくはこちら!
このような協力体制により、具体的な成果を上げる事例が増えており、実践においても参考となる成功例が多数存在します。
コラボヘルスのメリット
コラボヘルスの導入により、健康保持の精度向上、生産性の向上、ブランドイメージの向上など、さまざまなメリットが期待できます。

生産性向上
コラボヘルスは、健康増進施策の精度を向上させるために、企業と健康保険組合が連携して組合員の健康データを活用します。データ分析を通じて、組合員一人ひとりの健康状態を把握し、個別に最適化された健康サポートを提供することで、施策の効果を最大化することが可能です。
従業員の健康状態が改善されることで、欠勤率の低下や業務効率の向上が期待でき、生産性の向上につながります。
医療費削減
コラボヘルスでの健康データの活用により、個人に合った健康サポートが出来るようになり、個々にあった予防医療や健康増進プログラムの実施ができるので、生活習慣病の予防や健康増進につながり、長期的な医療費を削減できます。
ブランドイメージ向上
コラボヘルスを通じて従業員の健康管理が徹底されている企業は、社会からの信頼を獲得しやすくなり、企業のブランドイメージ向上へと繋がります。
これにより企業の競争力が向上し、企業の社会的責任とブランド力の向上は相互に関連し、持続可能な成長を促すと考えられます。
コラボヘルス導入の基本ステップ
ここからはコラボヘルスを効果的に導入するための基本ステップを紹介します。
推進体制の整備

明確な組織体制を整備し、責任者を設置する
組織体制や責任者が明確になっていることで、プロジェクトの進行管理や各施策の実施において統一された指針を持つことができます。
関連部門やステークホルダーとの連携方法を具体的に策定する
定期的なミーティングの開催や情報共有のプラットフォームを活用することで、各部門間のコミュニケーションを円滑にし、協力体制を強化します。
組織内でのコミュニケーションや情報共有の重要性を強調
効果的な情報伝達手段を導入することで、全員が同じ目標に向かって協力し合い、コラボヘルスの推進がスムーズに進行していきます。
推進体制の整備において具体的な実務的な対策を講じる
役割分担の明確化や責任範囲の設定、進捗管理のためのツール導入などを行い、実際の運用において役立つ体制を構築します。
健康情報の可視化

健康情報の可視化は、組合員の健康データを効果的に収集・管理するプロセスです。具体的には、アンケート調査や健康診断の結果、ウェアラブルデバイスから得られるデータなど、さまざまな情報源からデータを収集します。
これらのデータは、システム上で一元管理し、個人情報の保護を徹底しながら、必要な情報を適切に整理・保存します。
そのようにしてデータを可視化することで、健康に関する課題の把握や施策の効果測定が容易になります。視覚的なグラフやダッシュボードを活用することで、複雑なデータも直感的に理解でき、迅速な意思決定を支援します。
これにより、組合員の健康状態のトレンドを把握し、効果的な健康増進施策を計画・実施することが可能となります。
目標・計画の立案

目標・計画の立案では、コラボヘルス導入における具体的な目標設定をします。計画策定時に考慮すべき要素として、従業員のニーズ、企業の状況、データ分析結果などが挙げられます。
さらに、目標達成に向けたロードマップの作成方法やチェックポイントについても考慮します。これらを通じて、計画を立案しましょう。
施策の実施と効果測定

施策の効果測定
施策の効果を測定するためには、具体的な指標や評価方法を設定する必要があります。これには、健康指標(BMI、血圧、血糖値など)の変化や、組合員の健康意識調査の結果、施策参加率、離職率の変動などが含まれます。
定量的なデータと定性的なフィードバックを組み合わせることで、施策の効果を総合的に評価することが可能です。
改善策の立案や施策の見直し
効果測定の結果を基に、改善策の立案や施策の見直しを行うことが求められます。例えば、健康指標に改善が見られない場合は、施策内容の再検討や新たなアプローチの導入が必要となります。また、組合員からのフィードバックを活用して、施策の参加しやすさや満足度を高めるための調整を行います。
継続的な改善プロセスを通じて、コラボヘルスの効果を最大化し、持続可能な健康増進施策を実現しましょう。
コラボヘルスに取り組む他社事例3選
花王株式会社/花王健康保険組合
花王グループでは平成20年から自社の健康開発推進部と健康保険組合が連携し、健康づくりに積極的な活動を続けてきました。
健康づくりでは
・生活習慣病への取り組み
・メンタルヘルスへの取り組み
・禁煙への取り組み
・がんへの取り組み
・女性の健康への取り組み
の5つの取り組みがあります。
健康づくりの取り組みで独自のポイント制を取り入れており、健康診断に問題がなければ300ポイント、タバコを吸わなければ300ポイントというように健康への取り組みを見える化しました。従業員は楽しみながら健康経営に参加できます。
参考:花王株式会社「花王グループ健康経営のご紹介」 参考:花王株式会社「花王グループ健康宣言」YKK株式会社/YKK健康保険組合
人事部、産業医、YKK健康保険組合などの健康に関わる機能と各事業の健康推進責任者で構成される「YKKグループ健康推進協議会」を設置しグループ全体の健康づくりを推進しています。
各会社およびYKKグループ健康推進協議会では
・生活習慣病の減少
・メンタル疾患の抑制
・予防的行動をとっている人の増加
などを行動目標として掲げています。
参考:健康への取り組み | YKK株式会社SCSK株式会社
SCSK株式会社は、残業時間を削減し、その分浮いた残業代を社員に全額還元する「スマートワークチャレンジ」・在宅勤務、サテライト勤務を推奨する「どこでもWORK」・よい行動習慣と健診結果に対するインセンティブを支給する「健康わくわくマイレージ」という取り組みを2013年から開始しています。
参考:サステナビリティ:健康経営の課題と取り組み | SCSK株式会社コラボヘルス導入におすすめ!LAVAの法人会員サービス

コラボヘルスの取り組みとして、LAVAでは全国のホットヨガスタジオLAVAをお得な価格でご利用いただける、法人会員サービスを提供しています。
LAVA法人会員サービスのおすすめポイント
国内No.1※1のスタジオ数!日本全国の都道府県に出店
全国540店舗以上※2どの店舗もアクセス抜群な立地や大型商業施設・地方都市に展開しています。
※1 東京商工リサーチ調べ(2024年4月※2 2025年3月時点(Rintosullブランド含む)
運動習慣が無くても続けやすい
レッスン時以外にも、インストラクターに何でも相談できるアットホームさが長く愛される一番の理由です。直接雇用のインストラクターが全国3,000名以上在籍しており、お客様満足度でも高評価をいただいております。
また、様々な生活スタイルに合うレッスンスケジュールも続けやすい理由のひとつです。
利用状況をデータで可視化
ご利用者の氏名、生年月日、各月のご受講回数等がCSVデータにより一目で分かります。データ処理もしやすく、契約している健保組合様からは運動習慣定着化の確認がしやすいといったお声をいただいております。
詳しいサービスの詳細はこちらから!
まとめ
・コラボヘルスは、企業と健康保険組合が連携して組合員の健康保持増進を目指す施策であり、健康経営の推進に寄与する。
・健康データの共有・分析を通じて個々の組合員に最適化された健康支援を提供し、企業の健康経営戦略を強化することが可能!
・健康保持の精度向上、生産性の向上、医療費削減、ブランドイメージの向上などのメリットが期待できる!
組合員の健康を保ち、医療費の削減にもなるコラボヘルス、是非導入を検討されてみてはいかがでしょうか?