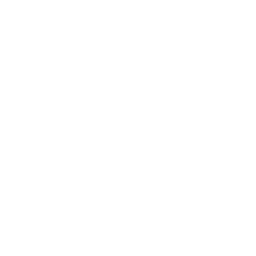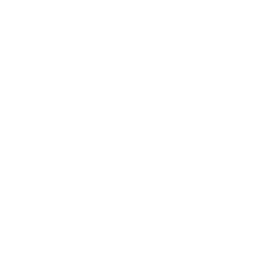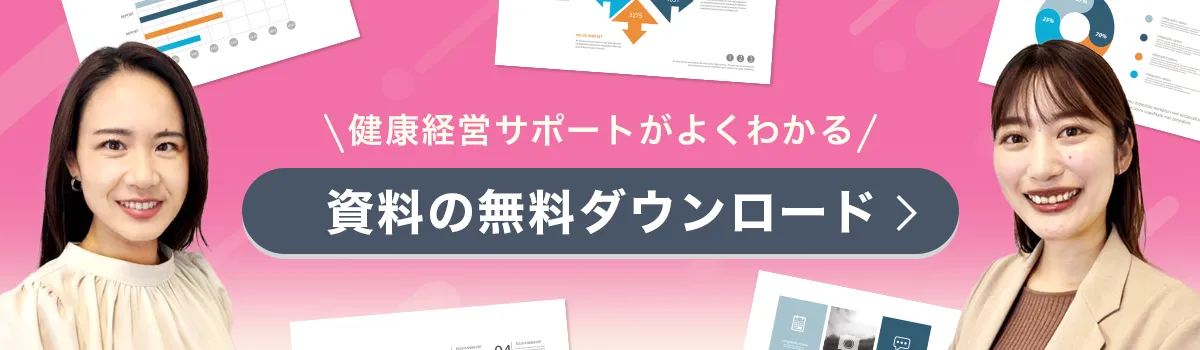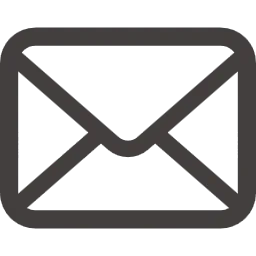【人事担当者必見】早期離職を20%削減!効果的な新卒社員定着戦略

新卒採用担当者にとって、早期離職は深刻な課題です。新卒を迎えたばかりなのに、数年も経たず辞めてしまう──そんな“早期離職”に頭を抱える人事は少なくありません。採用・育成に費やしたコストが水の泡になり、現場もストップしてしまいます。
一方で、新卒社員の定着率を向上させることは、企業の持続可能な成長に直結します。定着率の向上により、組織の安定性が増し、社員のスキルや知識が蓄積されることで、長期的な競争力を高めることが可能です。
本記事では、「早期離職を20%削減するための効果的な新卒社員定着戦略」について解説します。具体的には、採用活動の見直しやオンボーディングプログラムの強化、柔軟な働き方の導入など、実践的な戦略を詳しく紹介します。
これらの戦略を実行することで、採用担当者が直面する早期離職の問題を解決し、優秀な新卒社員の長期的な定着を実現するための有益な情報を提供します。
早期離職とは?その実態と課題

早期離職とは、入社後3年以内に退職することを指し、現在多くの企業がこの問題に直面しています。最新の統計データによれば、新卒社員の早期離職率は約35%と高水準にあり、これは企業の持続可能な成長に大きな影響を及ぼします。
本記事では、早期離職の実態とその背景にある課題を整理し、企業が直面する問題の深刻さを明らかにします。
早期離職の定義と現状
早期離職とは、入社後3年以内、特に半年以内に退職することを指します。これは、新卒社員が組織に適応する前に離職してしまう現象であり、企業にとって大きな課題となっています。
最新の統計データによると、2018年3月卒業の新規大卒就職者の3年以内離職率は31.2%に達しました。これは、2010年以降も30%強で推移しており、安定的に高い水準を維持しています
年代別では、20代の正社員の約11%が早期離職の経験があり、他の年代と比較して最も高い割合となっています。また、大卒者全体の3年以内離職率が約30%強推移している中でも、20代の離職率は特に高い傾向にあり、若年層は職場環境や仕事内容とのミスマッチを感じやすく、その結果として離職に至るケースが多いです。
参考:若手人材の早期離職の実態~調査結果から見えた早期離職検討者と企業に必要な考え方とは~産業別に見ると、サービス業において早期離職率が高い傾向があります。また、事業所の規模が小さいほど離職率が高くなる傾向が確認されています。これは、規模の小さい企業ではキャリアパスやサポート体制が十分でない場合が多いためと考えられます。
以下の表は、産業別及び従業員別の早期離職率の現状を示しています。
| 産業分類 | 離職率(%) |
|---|---|
| 宿泊業・飲食サービス業 | 51.5 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 46.5 |
| 教育・学習支援業 | 45.6 |
| 医療・福祉 | 38.6 |
| 小売業 | 37.4 |
これらの業種は、労働環境の厳しさや給与水準、人間関係の問題などが離職率の高さに影響していると考えられます。
参考:サービス業の離職防止への取り組み~現状と離職率が高い理由も紹介| 従業員数 | 離職率(%) |
|---|---|
| 1,000人以上 | 14.2 |
| 300~999人 | 16.1 |
| 100~299人 | 19.0 |
| 30~99人 | 16.0 |
| 5〜29人 | 15.6 |
一般的に、企業規模が小さいほど離職率が高くなる傾向があります。
参考:離職率の平均値と企業の課題これらのデータは、企業が早期離職を防ぐための戦略的な対応を講じる際の重要な基礎情報となります。特に、若年層の離職率が高いことや特定の産業・企業規模での傾向を踏まえた対策が求められています。
早期離職が企業に与える影響
企業のコスト負担
早期離職は企業に多大なコスト負担をもたらします。新卒社員の採用には、求人広告の費用や採用担当者の人件費、面接や選考プロセスにかかる時間とリソースが必要です。さらに、採用後には研修やオンボーディングプログラムへの投資が行われますが、早期離職によってこれらの投資が無駄になるリスクが高まります。
2018年3月卒業の新規大卒就職者の3年以内離職率が31.2%であったことからも、企業は継続的な人材定着に向けた戦略を強化する必要性が浮き彫りになります。
残留社員への負担
早期離職は残留社員のモチベーション低下や業務負担の増加を引き起こします。新人が短期間で退職すると、チーム内での業務分担が急に変わり、他の社員に余分な負担がかかります。これにより、残留社員のストレスや疲労が蓄積し、結果として全体の生産性が低下する可能性があります。
企業イメージへの影響
早期離職は企業のイメージやブランド価値にも悪影響を与えます。高い離職率は外部から見ると企業の魅力や働きやすさに対する疑問を引き起こし、優秀な人材の採用が難しくなる要因となります。また、既存の社員や顧客からの信頼を損なうことで、長期的なビジネスの成長にも影響を及ぼす恐れがあります。
若者の早期離職率の特徴

産業別や企業規模別に見ると、若者の早期離職率には顕著な差異が見られます。以下の表は、主要産業別および企業規模別の20代の早期離職率を示したものです。
| 産業 | 大企業 | 中小企業 |
|---|---|---|
| サービス業 | 25% | 40% |
| 製造業 | 20% | 35% |
| IT・通信業 | 15% | 30% |
このデータから、中小企業においてはどの産業でも20代の早期離職率が高い傾向にあることがわかります。特にサービス業では、大企業と比べて中小企業での離職率が大幅に高くなっています。これは中小企業がリソースやサポート体制に限界があるため、若手社員のニーズに十分に応えられないケースが多いことが背景にあります。
若者の視点やニーズに応じた職場環境の整備や、成長機会の提供が早期離職率の低下に直結するため、企業はこれらの特徴を踏まえた対策を講じることが求められます。
新卒社員が早期離職する理由

若年層特有の離職理由としては、以下のような要因が挙げられます。
・人間関係の問題:上司や同僚とのコミュニケーション不足や理不尽な指摘が、職場離れの一因となります。
・職場環境とのミスマッチ:期待していた職場の雰囲気や文化と実際の環境が異なる場合、ストレスを感じやすくなります。
・成長機会の不足:スキルアップやキャリアパスの明確化が不十分だと、将来に対する不安が増し、離職の動機となります。
新卒社員が早期離職する理由は上記のように多岐にわたります。離職理由ランキングから明らかになる特有の傾向やパターンが挙げられ、これらの要素は、新卒社員の定着を阻む大きな要因となっており、効果的な対策が求められます。
離職理由ランキングから見る傾向
離職理由ランキングを基に、早期離職の傾向を詳しく分析します。最新の調査データによると、新卒社員が離職を決意する主な理由は以下の通りです。
| 離職理由 | 割合(推定) |
|---|---|
| 人間関係が好ましくなかった | 約30% |
| 人間関係が好ましくなかった | 約25% |
| 人間関係が好ましくなかった | 約20% |
| 給与に不満 | 約15% |
| その他 | 約10% |
2025年の新卒社員の離職理由で最も多かったのは「人間関係が好ましくなかった」(約30%)でした。Z世代は職場の雰囲気や人間関係を重視する傾向が強く、上司や同僚との関係が悪いと早期に離職を選ぶ傾向があります。
次いで「労働条件の悪さ」(25%)や「仕事内容への不満」(20%)が続き、働き方や成長実感への期待がうかがえます。企業は、柔軟な働き方の導入や、キャリア支援、コミュニケーションの質向上を通じて、離職防止に取り組む必要があります。
これらの結果から、特に仕事内容の明確化と上司との良好な関係構築が優先的に対策すべき領域であることが明らかになります。
人間関係の問題と対策
新卒社員の早期離職において、人間関係の問題は非常に大きな要因となっています。よくある問題と対策は以下をご覧ください。
- 人間関係の問題
-
- 上司や先輩とのコミュニケーション不足
- 理不尽な指摘によるストレス
- チーム内の協力体制の欠如
- 職場内でのハラスメント問題
- 社員同士の信頼関係の損失
- メンタルヘルスの悪化によるパフォーマンス低下・モチベーション喪失
- 人間関係改善のための対策
-
- メンタリング制度の導入
- メンタルヘルス研修の実施
- チームビルディング活動の実施
- 定期的なメンタリングセッションによる信頼関係の構築
- 月1回のチームランチなど、社員同士の交流促進
人間関係の改善は、新卒社員の定着率向上に直結します。信頼と安心感のある職場づくりが、離職防止の鍵となります。
入社後のギャップとミスマッチ
新卒社員が入社前に抱いていた仕事内容への期待と、実際に配属された業務の現実との間に大きなギャップが生じることがあります。
例えば、入社前に営業職として広範な顧客対応や企画立案を期待していた新入社員が、実際には事務作業や基礎的な業務に従事するケースが見受けられます。このようなギャップは、社員のモチベーション低下や職務満足度の低下を引き起こし、早期離職の原因となることが多いです。
また、企業文化や職場環境とのミスマッチも離職につながる大きな要因です。
例えば、オープンなコミュニケーションを重視する企業であっても、実際の職場では上司との距離感が遠かったり、チーム内での協力体制が不十分であったりする場合、新卒社員は孤立感を感じやすくなります。このような状況は、社員が自分の成長やキャリアビジョンを描きにくくし、結果として離職を考える要因となります。
これらのギャップやミスマッチを埋めるためには、以下のような具体的な対策が有効です。
・リアリスティックジョブプレビュー(RJP)の導入:入社前に実際の業務内容や職場環境を詳しく説明することで、期待と現実のズレを最小限に抑える。
・メンター制度の活用:新入社員に対して経験豊富なメンターを配置し、日常的なサポートやフィードバックを提供する。
・定期的なフィードバックセッションの実施:入社後一定期間ごとに社員と上司が対話を持ち、業務内容や職場環境への適応状況を確認し、必要に応じて調整を行う。
・オンボーディングプログラムの充実:初期研修やチームビルディング活動を通じて、社員が早期に職場に慣れ、組織文化に適応できるよう支援する。
これらの施策を通じて、新卒社員が入社後のギャップやミスマッチを感じることなく、企業に対する信頼感と帰属意識を高めることが可能となります。結果として、早期離職の防止につながり、企業の持続可能な成長を支える人材定着が実現します。
早期離職を防ぐための採用活動とオンボーディング戦略

オンボーディングは新卒社員が組織に馴染み、職務で成功をつかむための支援プロセスです。早期離職を防ぐには採用活動と戦略的なアプローチが欠かせません。適切な選考プロセスとリアルな職務情報提供を通じてミスマッチを減らし、入社後のギャップを最小化します。
また、充実したオンボーディングプログラムと柔軟な働き方の導入は社員のワークライフバランスを改善し、定着率を向上させます。さらに、健康経営の施策を取り入れることで心身のストレスを軽減し、職場でのパフォーマンス向上に繋げることができます。これらの包括的な戦略により、企業は持続可能な成長を達成し、優れた人材を長期的に確保できます。
採用活動での工夫
採用活動での工夫は、優れた新卒社員を獲得し、早期離職を防ぐための重要なステップです。
まず、効果的な求人広告の作成方法として、ターゲットとなる求職者のプロファイルを明確にし、そのニーズや期待に応える内容を盛り込むことが求められます。具体的には、求めるスキルや経験だけでなく、企業のビジョンや文化を詳細に伝えることで、応募者が自分に適した職場かどうかを判断しやすくなります。
・オフィスツアー:実際の職場の雰囲気や設備を応募者に見せ、具体的なイメージを持ってもらう。
・社員インタビュー:日常業務やキャリアパスのリアルな声を共有し、応募者が将来像を描きやすくする。
・適性検査:職務に必要なスキル・能力を測定し、応募者の強み・弱みを客観的に評価する。
・構造化面接:一貫性のある質問を行い、公平で透明性の高い評価を可能にする。
・リアリスティックジョブプレビュー(RJP):実際の業務内容や職場環境を事前に詳しく伝え、ミスマッチのリスクを低減。
入社後のオンボーディングプログラム
入社後のオンボーディングプログラムは、新卒社員が組織に迅速かつ円滑に適応し、早期離職を防ぐための重要な取り組みです。効果的なオンボーディングにより、社員のエンゲージメントが向上し、長期的な定着が期待できます。
具体的な構成要素は以下です。
・初期研修:会社のビジョンや業務内容について深く理解する機会を提供します。
・メンター制度:経験豊富な先輩社員から新入社員がサポートを受けられる環境を整備します。
・定期的なフィードバック:社員の成長を促進し、課題の早期発見と対策に役立ちます。
・成果測定:社員満足度調査や定着率の追跡を通じてオンボーディングの成果を確認します。
・フィードバック収集方法:定期的な1対1の面談やアンケート調査を活用し、プログラムの改善点を継続的に見直します。
実際に日本オラクル株式会社では、現場の上司とは別に、ナビゲーターとサクセスマネージャー(教育担当とサポート担当)という2人のメンターを配置。新入社員には目的別に質問できるメリットがあり、サポート役が役割を分担することで、きめ細かいアドバイスを提供しています。この取り組みにより、社員エンゲージメント率85%という高い成果を上げました。詳しくは、コチラをご覧ください。
柔軟な働き方の制度導入
柔軟な働き方の制度導入は、現代の多様化する職場環境において新卒社員の定着率向上や離職率低下に不可欠な戦略です。フレックスタイム制度やリモートワーク、時短勤務など、さまざまな柔軟な働き方を提供することで、社員一人ひとりのライフスタイルやニーズに対応し、働きやすい環境を整えることができます。
具体的な制度の種類とその特徴は以下の通りです。
・フレックスタイム制度:出勤・退勤時間を柔軟に選択できるため、通勤時間の短縮やライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
・リモートワーク:オフィスに出勤せずに自宅やカフェなど、場所を選ばずに業務を行うことで、ワークライフバランスの向上を図ります。
・時短勤務:フルタイムではなく、短時間で働くことを選択できる制度で、家庭や自己啓発との両立を支援します。
これらの柔軟な働き方は、新卒社員が自身のキャリアとプライベートを両立させやすくすることで、職場への満足度を高め、早期離職を防ぐ効果があります。
実際に中外製薬は、テレワークの推進や長時間勤務の削減、有給休暇取得の促進に取り組み、所定外労働時間の減少や有給休暇取得率の向上を実現しています。これにより、社員のワークライフバランスが改善され、定着率の向上に寄与しています。
参考:働き方改革柔軟な働き方の制度導入は、単なる制度の提供にとどまらず、社員一人ひとりのニーズに寄り添ったサポート体制を構築することが重要です。これにより、企業全体の持続可能な成長と社員の長期的な満足度向上を実現することが可能となります。
メンタルヘルスプログラムによる健康経営のメリット
健康経営の施策においてメンタルヘルスに特化することの主なメリットは、社員のストレスを軽減し、心身の健康をサポートすることにあります。特にメンタルヘルスプログラムの導入により、社員のパフォーマンスが向上し、職場全体の生産性が高まります。さらに、社員のメンタルウェルビーイングを促進することで、職場へのエンゲージメントが強化され、長期的に見て離職率を低下させる効果が期待できます。
こうした健康経営の導入は、企業にとって持続可能な人材管理と競争力の向上に寄与します。
健康経営の取り組み事例:新入社員のストレス緩和にLAVAのオンライン・出張ヨガサービスを導入した企業の声
新入社員の早期離職防止に向けた、健康経営の実践
新入社員の早期離職は、多くの企業が直面する大きな課題です。その背景には、「入職後の人間関係・環境変化によるストレスの増大」や「心身の疲弊」が挙げられます。
こうした中、小倉記念病院では健康経営の一環として「LAVAのオンライン・出張ヨガサービス」の導入を実施し、新入社員のストレス緩和とメンタルヘルス対策に成功しました。
ヨガ導入の背景:「3か月後の山場」を乗り越える支援
この企業では、入職3か月後にストレスがピークに達する傾向にあることから、フォローアップ研修の一環としてヨガプログラムを導入。
「社会人としての健康意識の醸成」と「緊張感の緩和」を目的とし、心身のリセットを促しました。
担当者のコメントでは、
「緊張した日々でこわばった心と身体を、ヨガでほぐしてもらいたい。健康な身体づくりのきっかけにもなればと考えています。」
と、健康経営に対する前向きな姿勢がうかがえます。
担当者の所感:「感動と笑顔が生まれる体験」
LAVAのオンライン・出張ヨガサービスを初めて体験した新入社員たちは、終了後には明らかに表情が明るくなり、生き生きとした姿が印象的だったとのことです。
担当者は次のように語ります。
「本格的なヨガを通じて、新入社員が笑顔になり、リフレッシュした姿を見て、取り組みの意義を強く感じました。」
健康経営のキーワードとしての「ストレス緩和」と「体験型プログラム」
本事例は、「健康経営=数値管理」だけではなく、「感覚的な満足度」「心のケア」も重要であることを示しています。
入職後のストレス緩和に向けた、体験型の取り組みは、早期離職防止・定着率向上にも大きく寄与します。
企業の人事・労務担当者は、こうした心身の両面から新入社員を支える健康経営の取り組みをぜひ参考にしてみてください。
早期離職者へのフォローと再定着支援
早期離職者へのフォローと再定着支援は、企業が抱える離職問題を根本的に解決するための重要なステップです。
離職者とのヒアリングや原因分析を通じて、離職の真の原因を明らかにし、再定着への具体的な対策を講じることが求められます。
また、キャリアカウンセリングや再入社プログラムなどの再定着支援策を導入することで、社員との信頼関係を築き、長期的な離職防止につなげることが可能です。
離職者へのヒアリングと分析
早期離職を防ぐためには、離職者へのヒアリングと分析が不可欠です。正確な退職理由を把握することで、企業は根本的な課題を明らかにし、効果的な対策を講じることが可能となります。以下では、退職理由を正確に把握するためのヒアリング手法や質問項目、データ分析の方法、そして分析結果を基にした具体的な改善策について詳しく解説します。
退職理由を正確に把握するためのヒアリング手法と質問項目としては、以下のような方法が有効です。
・構造化インタビュー:あらかじめ用意された質問を基に、体系的に情報を収集します。これにより、全員から一貫したデータを得ることができます。
・オープンエンド質問:自由回答形式の質問を含めることで、社員個々の具体的な悩みや改善点を引き出します。
・匿名アンケート:匿名性を確保することで、正直な意見や感情を引き出しやすくなります。
具体的な質問項目の例としては以下が挙げられます。
・入社時の期待と実際の業務内容にギャップを感じた点は何ですか?
・職場場の人間関係に関して改善してほしい点はありますか?
・キャリアパスや成長機会についての満足度はいかがですか?
・会社の福利厚生や働き方に対する意見をお聞かせください。
集めたデータを分析し、共通する課題や傾向を明らかにする方法としては、定量的・定性的なデータ分析が有効です。
定量的なデータは統計的手法を用いて離職理由の頻度や傾向を把握し、定性的なデータは内容分析やテーマ分析を行い、深層的な原因を探ります。
例えば、退職理由の中で「職場環境のミスマッチ」が特に多い場合、その具体的な問題点をさらに掘り下げることが重要です。
分析結果を基にした具体的な改善策の立案や実施方法については、以下のステップが推奨されます。
・課題の優先順位付け:分析結果から明らかになった課題を重要度や影響度に応じて優先順位を付けます。
・具体的な対策の策定:例えば、職場環境の改善が必要であれば、フレキシブルな働き方の導入やコミュニケーション研修の実施など、具体的な施策を計画します。
・実施と評価:策定した対策を実行し、その効果を定期的に評価・見直します。必要に応じて改善を加えることで、持続的な離職防止につなげます。
これらのプロセスを通じて、企業は早期離職の根本原因を特定し、効果的な改善策を実施することで、新卒社員の定着率向上に大きく寄与することができます。
再定着支援の重要性
再定着支援とは、早期に職場を離れた社員が再び組織に順応し、長期的に貢献できるよう支援する取り組みを指します。
定着支援を成功させるためには、個別対応と継続的なサポートが不可欠です。個々の社員のニーズや課題に応じた柔軟な対応を行うことで、社員一人ひとりの満足度と定着意欲を高めることができます。
実際に、三井化学株式会社は、従業員の定着率向上と再定着支援を目的に、柔軟な働き方の導入やキャリア支援制度の整備を積極的に進めてきました。同社では、育児や介護などのライフイベントで一時的に離職した社員に対して、**「カムバック制度」**を導入。これは、退職後も一定期間、再雇用の機会を提供する制度で、社員が安心してライフイベントに向き合える環境を整えています。
また、再雇用された社員に対しては、復職後のスムーズな業務復帰を支援するためのオンボーディングプログラムや、キャリアカウンセリングの機会も提供。これにより、再定着後のパフォーマンス向上と長期的な定着を実現しています。
このような取り組みは、単に離職率を下げるだけでなく、社員のエンゲージメントを高め、企業全体の生産性やブランド価値の向上にもつながっています。実際に、三井化学は人材の確保・定着に関する好事例として、厚生労働省の事例集にも掲載されています。
離職防止のための長期的な対策
長期的な離職防止策は、企業の持続可能な成長に欠かせない要素です。
特に、リクルートが実施している社員育成プログラムは、社員のスキル向上とキャリアパスの明確化に繋がり、長期間にわたる社員の定着を促進します。同社では、段階的なトレーニングとキャリアサポートを提供することで、社員一人ひとりが持つポテンシャルを最大限に引き出すことができています。
また、サイバーエージェントが導入したフィードバックと改善のサイクルは、社員一人ひとりの声を反映した柔軟な環境づくりを可能にしています。定期的に実施される満足度調査や面談を通じて、社内の課題を早期に発見し、迅速に対応する体制を整えることができ、実際に社員の離職率低下に貢献しています。
参考:87%の社員が「働きがいがある」と答える環境を実現ーーCHO曽山が語るエンゲージメントを高める人事施策さらに、企業文化の醸成や働きやすい環境作りといった包括的な対策として、トヨタ自動車ではチームビルディング活動の推進や柔軟な働き方の導入を行っています。これにより、社員のエンゲージメントを高め、職場全体の雰囲気を向上させる効果が確認されています。
参考①:トヨタタイムズ「チーム経営」特集 参考②:トヨタ公式サイト「人材育成と働き方」これらの対策を通じて、企業全体としての戦略的な取り組みを強化することが、早期離職の防止と社員の長期的な定着に繋がります。持続可能な定着戦略を実現するため全社的な視点での計画と実行が必要です。
まとめ:企業が早期離職を防ぐためにできること
本記事でご紹介したように、早期離職の防止は単なる人材確保の課題ではなく、企業の持続的な成長に直結する重要な取り組みです。採用後のフォロー体制の充実や働きやすい環境づくりは、社員一人ひとりの定着と活躍を支える鍵となります。
早期離職率を20%削減するためのポイント
・適性検査やリアルな情報提供の徹底
・オンボーディングプログラムの強化
・フレックスタイムやリモートワークの導入
・メンタリング制度の充実
・メンタルヘルスプログラムによる健康経営
これにより、社員の不安を軽減し、定着率向上に寄与します。
離職防止に向けた企業の長期的な取り組み
持続可能な育成プログラムやキャリア支援、定期的なフィードバックの整備が、社員の定着を促進します。これにより、企業全体の成長を支える基盤を築くことができ、持続可能な成長を実現することが可能となります。