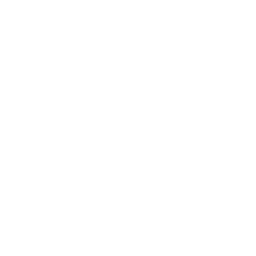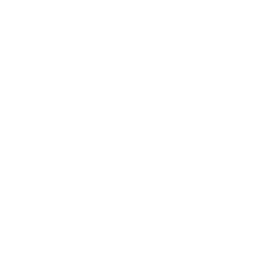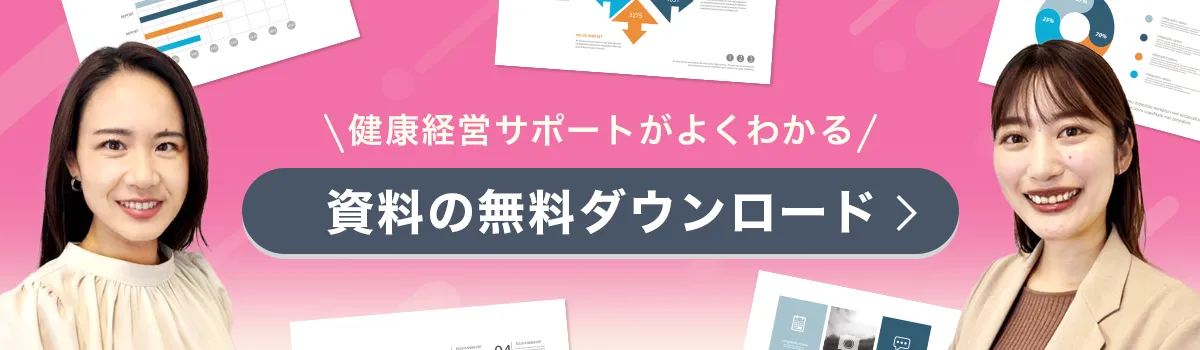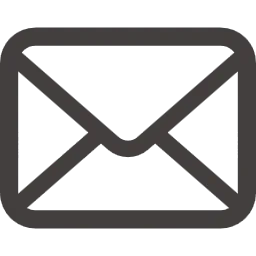ロコモ予防で従業員の健康と生産性を守る:法人向けヨガ導入のすすめ

採用難が続く今、従業員の健康は企業の競争力に直結しています。 健康経営に取り組む企業では、医療費や離職率が低く、財務面でも優位性があります。 最近厚労省でも対策を講じる様うたわれているロコモティブシンドローム(ロコモ)は、移動機能の低下を引き起こし、要介護リスクを高めます。
そのロコモ予防において、ヨガが適しており、生産性向上にも効果的です。本記事では、ロコモ予防としてのヨガ導入方法と制度活用のポイントをわかりやすく解説します。
ロコモティブシンドロームとは

ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは、加齢や生活習慣により骨・関節・筋肉などの運動器が衰え、立つ・歩くといった基本動作が困難になる状態です。
進行すると筋力やバランス機能が低下し、転倒や要介護のリスクが高まります。
ロコモ該当者の増加による企業負担については、健康保険組合や厚生労働省の資料を参考に試算されています。医療費・介護費・休業補償・生産性損失などを合算すると、従業員1人あたり年間約115万円、1000人規模の企業では最大2億円超のコスト増につながる可能性があるとされています。
ロコモは「ロコモ度1〜3」で評価され、初期段階では見逃されやすいため、早期発見と運動による予防が重要です。
企業が従業員のロコモ進行を把握し、対策を講じることは、健康経営の基盤づくりに直結します。
厚生労働省が推奨するロコモ予防
厚生労働省はロコモ予防のために、週150分以上の中強度運動と週2回の筋力トレーニングを推奨しています。
中強度運動とは、息が弾む程度の速歩や自転車通勤などで、10分ずつの分割でも効果があります。筋トレはスクワットやランジなどの自重運動で、下肢と体幹を中心に行うのが理想です。
企業では、勤務時間内に「10分アクティビティ枠」を設けることで実践率が向上し、歩数連動アプリやインセンティブ制度の導入により行動定着が進みます。
これらの施策は「+10(プラス・テン)」という考え方に基づき、1日10分の追加運動でロコモや生活習慣病のリスクを大幅に低減できるとされています。
さらに、健康経営優良法人認定制度のKPIと連動させることで、医療費削減や離職率低下に加え、税制優遇などのメリットも得られます。
従業員の健康を守るためのロコモ予防

ロコモ予防のための運動習慣の重要性
ロコモ予防には、日常的な運動習慣の定着が不可欠です。
筋力・柔軟性・バランスのいずれかが低下すると、転倒や要介護のリスクが大幅に上昇します。例えば、大腿四頭筋が50%低下すると転倒リスクは3.6倍、片脚立ちが15秒未満だと要介護認定率が2.3倍になると報告されています。
しかし現代の働き方では、平均歩数が6,200歩と少なく、在宅勤務ではさらに減少します。座り時間が長いことで筋力低下が加速し、ロコモリスクが高まっています。
参考:厚生労働省令和5年 国民健康・栄養調査ロコモ予防には、歩数や座り時間の可視化、スマートウォッチやチャットボットによるリマインド、週2回の筋トレ+ヨガなどの仕組みづくりが効果的です。運動習慣は「やる気」ではなく「仕組み」で定着します。企業が早期に環境を整えることで、従業員の健康と生産性を同時に守ることができます。
運動不足がもたらす身体的フレイルのリスク
特に下肢では40歳以降、10年で最大8%の筋肉が萎縮する「サルコペニア」が進行し、基礎代謝が低下します。これにより脂肪が蓄積されやすくなり、糖尿病や高血圧などの生活習慣病のリスクが連鎖的に高まります。筋力低下が深刻化すると「フレイル期」に突入し、転倒や骨折が多発します。
運動器疾患と日常生活への影響
変形性膝関節症や慢性腰痛といった運動器疾患は、働く世代にも広く見られます。痛みが生じると身体動作だけでなく集中力も奪われます。プレゼンティーイズムにも直結する為、従業員の健康を保つことは、企業自体への還元にもなります。
参考:ロコモティブシンドロームとプレゼンティーズムとの関連ロコモ度テストの概要と目的
ロコモ度テストは、日本整形外科学会が推奨する「移動機能の健康診断」です。
テスト内容は2ステップテスト・立ち上がりテスト・ロコモ25質問票の3要素からなっており、それぞれ目的も異なっております。
ヨガがロコモ予防となる理由

下肢筋力の強化による移動機能の改善
大腿四頭筋やハムストリングスといった下肢の大筋群は、歩行や階段昇降など移動機能の要となる筋肉です。ヨガのポーズでは立ちポーズやバランスポーズといった下肢の筋力向上を図るポーズはもちろん、ストレッチ要素も含まれている為筋肉をまんべんなく使う事ができます。
ストレス軽減による生産性向上
厚生労働省のサイト内にもヨガの健康効果としてストレス軽減・うつへの有用効果が記載されています。
参考:厚生労働省eJIMまたヨガの心理的効果についての調査研究において、以下の心理指標が向上していました。
- 自尊感情
- 人生満足度
- 前向きな生活意欲
身体的フレイルの予防効果
Brigham and Women's Hospital(ハーバード大学医学部の教育病院)のレビューによると、ヨガによるフレイル予防として、以下の効果が確認されました。
- 歩行速度改善
- 下肢筋力の改善
- 持久力の改善
法人向けヨガプログラム導入時の考慮点

インストラクター選び
費用対効果を考慮するのはもちろんですが、効果を上げるためにはインストラクターの選別も必要となってきます。インストラクターを選ぶ際は、スキルだけでなくリスク管理と運営柔軟性をセットで評価する視点が欠かせません。
チェックポイント
- RYT200などの資格を保有し運動器疾患に関する知識を持っているか
- 企業に所属しているインストラクターに依頼するか、個人で活動しているインストラクターに依頼するか
- 対面とオンラインの両方に対応し海外拠点や在宅勤務者もカバーできるか
- レッスンプログラムをロコモ予防向け・ストレス軽減向け等にカスタマイズできるか
- 企業文化や就業規則を理解し、労務リスクを避ける指導ができるか
事前に問い合わせなどをして、上記の確認をするようにしましょう。
インストラクター次第で効果が決まると言っても過言ではありません。企業にフィットする、信頼性のある経験豊富なヨガインストラクターを選びましょう。
従業員の生活に合わせた柔軟なスケジュール
シフト勤務と在宅勤務が混在する組織では、全員が同じ時間に集まることは現実的ではありません。最も取り組みやすい方法は、出社率が高い時間帯を分析して「コアタイムレッスン」を設定し、そこに参加できない人のために同内容をオンデマンド動画として公開する二本立ての仕組みです。
例えば、毎週水曜12時15分からの20分間をコアタイムに設定し、同日18時以降には録画を編集して社内ポータルにアップロードすると、フレックスタイムや夜勤明けの従業員も好きなタイミングで視聴できます。オンデマンド動画は5分・10分・20分の3種類に分けておくと、昼休みの隙間時間や子育て中の在宅ワーカーでも無理なく取り組めるため、視聴率が向上します。
運動セミナーとの組み合わせ
運動セミナーとヨガを組み合わせると、「知識を得た直後に体を動かし、数週間後に変化を確認する」という学習サイクルが成立します。例えば45分間の講義で骨・関節・筋肉の仕組みやロコモティブシンドロームの進行メカニズムを図解付きで解説し、従業員に自分ごと化させます。次に、30分間のヨガ体験会を実施し、下肢強化に直結する動きを実践します。講義と体験を同日に行うことで、「知る」と「やる」が脳内で強固に結び付いて、行動変容も起きやすくなります。
オンラインヨガでいつでもどこでも
オンラインヨガを導入する際、まず検討すべきは配信プラットフォームの選定です。Zoomは録画機能やブレイクアウトルームで個別指導がしやすく、Teamsは社内チャットやカレンダーと連動するため参加案内が自動化できます。どのツールを選ぶ場合でも、エンドツーエンド暗号化、SSO(シングルサインオン)対応、ISO27001など第三者認証取得の有無をチェックすると、情報漏洩リスクを最小限に抑えられます。
ロコモ予防を支援する制度

国や自治体、健康保険組合が用意している支援制度は大きく分けると以下の3つになります。
- 厚生労働省の助成金
- スポーツ庁や自治体が実施する運動促進補助金
- 健康保険組合が提供する運動プログラム
厚生労働省の「業務改善助成金」
厚生労働省の「業務改善助成金」では、従業員の健康保持を目的としたプログラム費用の一部が対象になり、最大600万円・助成率80%まで支給されるケースもあります。
オンライン環境整備やヨガスペースの整備・講師費用などが助成の対象となります。
スポーツ庁が実施する「Sport in Life」
目的:身体診断「セルフチェック」および「改善エクササイズ」の社会実装を目指し、運動習慣の定着と健康増進を図るモデル事業を創出する。
対象:Sport in Lifeコンソーシアムに加盟する地方公共団体または法人格を有する団体が代表となり、複数団体で構成されるプロジェクトチーム
補助内容:以下のテーマのいずれかを選び、セルフチェックを活用したモデル事業を実施。
・健康診断と連動した運動器チェック
・フィットネスジムでの体力測定との連動
・スポーツイベントでの導入
・職業別(運輸業など)の定期チェック
加えて、効果検証・情報発信・成果報告も実施。
補助率:最大 2分の1(50%)
上限額:1件あたりの申請金額に上限はないが、事業全体の予算規模は1,800万~2,200万円(税込)程度。採択件数は4~5件を予定。
申請条件:
・Sport in Lifeコンソーシアム加盟団体であること(構成団体も加盟が望ましい)
・過去に採択された団体も応募可能だが、異なる内容での応募が必須
・必要最小限かつ適切な積算による申請が求められる
活用メリット:
・国の支援を受けて、地域や団体の健康促進モデルを構築できる
・SNSや「ここスポ」などを通じた広報支援
・成果が次年度以降の事業に活用される可能性あり
申請ステップ:
①公募説明会への参加し、企画書作成
事業計画書、予算書、団体情報などを記載。
②申請書の提出
必要書類をメールで提出。
③委託契約の締結
スポーツ庁との契約手続きや事業開始に向けた社内体制の整備など。
④事業実施・報告・精算
補助金交付が決定した後に事業を開始し、中間報告と最終報告実施。
健康保険組合が提供する運動プログラム
多くの健康保険組合では、従業員が気軽に運動できるよう「契約フィットネスクラブ」と「オンライン運動クラブ」の両輪で支援を行っています。
【ホットヨガスタジオLAVA 法人契約事例】
- ・契約フィットネスクラブとして:伊藤忠連合健康保険組合
- 従来から契約しているスポーツ施設の男女別利用比率が男7:女3と偏りがあった為、女性が気軽に利用しやすいホットヨガスタジオLAVAのスタジオプランを利用しています。月会費に対する補助も設定していて、LAVA導入後は女性の利用者が6割に増加しました。
- ・オンライン運動クラブとして:株式会社静岡銀行
- 契約しているスポーツ施設において男性の利用者が多かった為、女性の健康の為にもホットヨガスタジオLAVAのスタジオプランとうちヨガプランを契約しています。うちヨガプランは、オンライン動画配信プランなので、いつでも好きな場所で気軽にヨガやエクササイズを楽しめます。
これらのプログラムは、データヘルス計画と連携することで、効果を数値で把握できます。
- フィットネスクラブでは、ICカードの入館記録や受講履歴をリアルタイムで取得。
- オンラインでは、視聴完了データ等をCSVで自動集計。
- これらのデータを健診結果やレセプト情報と突合することで、腹囲・ロコモ度などの変化を半年ごとにダッシュボードで可視化できます。
ホットヨガスタジオLAVA法人向けサービス導入の成功事例

利用者増加:東京都情報サービス産業健康保険組合
契約してから数年が過ぎた健康保険組合で、利用者数が右肩上がりです。
- 利用者数比較
- 1年目と2年目:約2.8倍
- 2年目と3年目:約1.2倍
平均受講回数は約6回/月です。多くの方が月に何回もレッスン受講をしているので、従業員の健康意識向上に役立っています。
従業員の運動習慣の定着:東京都教職員互助会
スタジオを貸し切って年8回に渡りレッスンを実施しました。レッスン参加権利獲得のための抽選も行うほどの大盛況でした。
参加後のアンケートでは「ヨガにまた参加したいと思いますか」という設問に対し1-6での評価において平均4.5を獲得しており、運動習慣定着へと貢献しております。また、ご受講者からは以下お声もいただいています。
- 30代女性
昨年も参加させていただき大満足だったので、今年も楽しみにしておりました。毎年楽しみのイベントとなっています。 - 60代女性
リフレッシュの点からとてもよかったので、機会を見つけて、参加したいと思いました。また、19時からだったことで、退勤後間に合う時間でありがたかったです。 - 40代女性
次回は、違うレッスンを受けたいです。
職場環境の改善:システム開発のベンチャー企業
システム開発を行うとあるベンチャー企業に2か月間伺い、朝9時~10時の間に15分~20分のヨガレッスン提供を行いました。
ご受講者からのアンケートにおいて、職場環境が改善されたような回答が複数ありました。
- 40代男性
MTG前に実施してもらったので、上長の機嫌がよかった。 - 30代男性
ヨガでリフレッシュできたからか、MTGの雰囲気が良くなった。 - 40代女性
仕事合間のリフレッシュなる、またチームの指揮も上がったように感じた。
まとめ
ロコモ予防は、企業の健康経営に欠かせないテーマです。ヨガは、筋力強化・柔軟性向上・ストレス軽減に効果があり、働く人の心身を整える手段として注目されています。
従業員の健康を守ることは、企業の未来を守ること。ヨガを通じて、無理なく、楽しく、ロコモ予防を始めてみませんか?