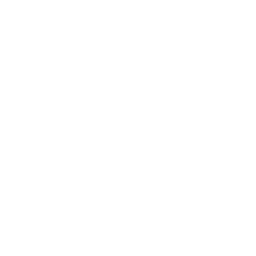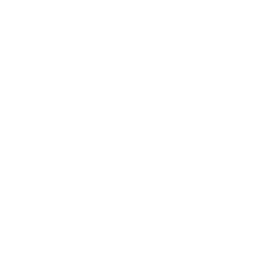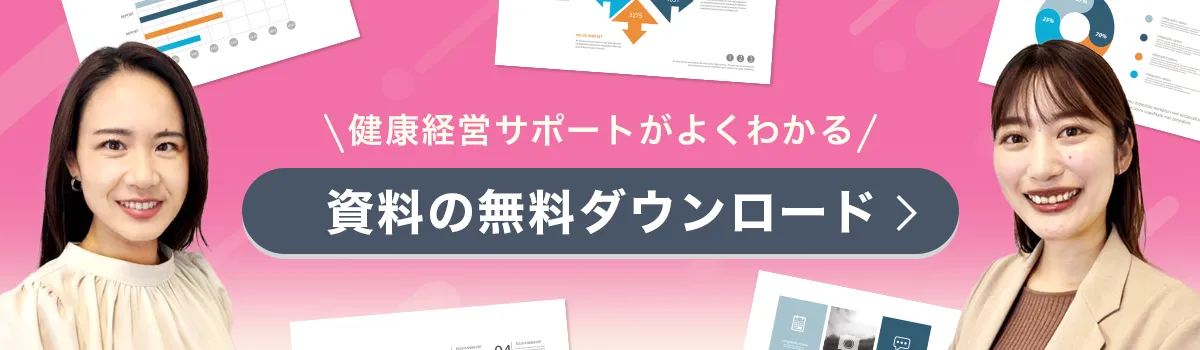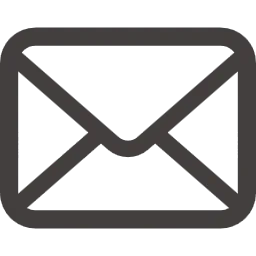メンタルヘルス対策が傷病手当の支給抑制につながる?ヨガとマインドフルネスの企業実践例

職場のメンタルヘルス不調による損失は、国内で年間約3兆円にのぼると厚労省が推計。こうした課題に対し、注目されているのが「社内ヨガ」の導入です。ハーバードの研究では、週2回のヨガでストレスホルモンが平均31%低下することが示され、実際に導入した企業では休職日数や傷病手当金の削減に成功しています。ヨガは、科学的根拠と実績を兼ね備えた、健康経営の新たな選択肢です。
メンタルヘルスケアの重要性と現状

職場におけるメンタルヘルス問題の深刻化
厚生労働省の調査によると、強い不安やストレスを感じる労働者は58.3%にのぼり、ストレス関連疾患による傷病手当金の受給件数は6年間で約1.6倍に増加しています。
精神障害による長期休職者も年平均8%のペースで増加しており、特に営業・カスタマーサポート・IT部門、30代前半の年齢層にリスクが集中しています。
こうした傾向は、企業の人件費や生産性に深刻な影響を及ぼし、放置すれば離職率の上昇や採用コストの増加といった負のスパイラルを招きかねません。実際、ストレスチェックや健康診断データを見直すことで、自社にも同様の傾向が潜んでいる可能性に気づく企業は少なくありません。
本記事では、メンタルヘルス不調がもたらす経営リスクを可視化し、傷病手当金コストの圧縮につながる具体策として注目される「ヨガ導入」について、科学的根拠と実践事例を交えて詳しく解説します。
メンタルヘルス不調が与える経済的影響
メンタルヘルス不調による企業負担は、
- 傷病手当金
- 代替要員コスト
- プレゼンティーズム損失
の三層構造で膨らみます。
モデル企業として従業員1,000名・平均年収550万円・平均欠勤日数(メンタル由来)年15日というケースを試算すると、まず傷病手当金の会社負担分※が年間約4,800万円に達します。
この損失は、単なる社内コストにとどまらず、IFRS(国際財務報告基準) S1(サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項)やESG評価で重視される「人的資本開示」にも直結します。SASB(サステナビリティ会計基準審議会)では、メンタルヘルス関連KPIとして「ストレス関連欠勤日数」が定義されており、海外投資家は財務指標と並列でその推移をチェックしています。
国内でも、日立製作所や資生堂などが統合報告書にメンタルヘルス施策と効果指標を掲載し、IR面談で高評価を得ています。
さらに、傷病手当金の増加は保険料率にも影響します。全国健康保険協会のモデルによると、給付額が1人あたり年1万円増えるだけで、翌年度の健康保険料率が0.03%上昇する可能性があり、1,000名規模の企業では約900万円の追加負担につながります。
参考:企業のメンタルヘルス対策義務とは?最新のストレスチェック制度や法的責任、対策方法を解説 | 【公式】江東区 中央区の精神科/心療内科/リワークならりんかい月島・豊洲クリニック 参考:職場におけるメンタルヘルス対策の現状等本記事では、こうした「見えない固定費」を可視化し、ヨガなどの施策によって傷病手当金やプレゼンティーズム損失を圧縮する方法を、実務的な視点で解説します。
健康経営の視点からの解決策の模索
メンタルヘルス対策が社内で停滞しやすい理由のひとつは、「何をもって成功とするか」が曖昧なことです。
たとえば、健康経営優良法人認定では「ストレスチェック受検率85%以上」「関連離職率のモニタリング」などの具体的な評価項目が定められており、国際規格ISO 45003でも「心理的リスクアセスメントの定期更新」「精神的健康に関するKPIの経営会議での報告」などが推奨されています。
こうしたガイドラインをもとに、欠勤日数・傷病手当給付額・エンゲージメントスコアを軸にダッシュボードを構築した企業では、意思決定のスピードが向上し、施策の改善サイクルが回りやすくなるという報告もあります。
実際の企業事例として、マルハニチロ株式会社では、プレゼンティーズム(出勤しているが生産性が低下している状態)をWHO-HPQで測定し、2021年から2024年にかけてスコアが64.4点から65.7点へと改善。アブセンティーズム(欠勤日数)も2023年度には平均2.8日と、勤怠データに基づく定量的な管理が行われています。さらに、ワークエンゲージメントスコアも安定的に推移しており、健康経営の成果を数値で可視化しています。
参考:マルハニチロ株式会社|健康経営の推進また、全国健康保険協会広島支部の調査では、経営層が健康経営に関与している企業ほど、退職率や医療費が低く抑えられる傾向があることが示されています。メンタルヘルス対策を強化した企業では、プレゼンティーズムの改善や人材定着率の向上が確認されています。
参考:健康経営「ひろしま企業健康宣言」| 協会けんぽ 広島支部施策選定においては、ヨガ・マインドフルネス・EAP・オンラインカウンセリングの4つが代表的です。
健康経営施策ごとのROI・ROH比較(参考値)
業界内の試算によると、初年度の投資利益率(ROI)は以下の通りです。
- ヨガ:2.8倍
- マインドフルネス:3.1倍
- EAP(従業員支援プログラム):1.6倍
- オンラインカウンセリング:1.9倍
また、慢性的なストレス指標が10%改善した場合の健康投資利益率(ROH)は
- ヨガ・マインドフルネス:4.0倍以上
- EAP:2.3倍
- オンラインカウンセリング:2.7倍
※これらの数値は参考値であり、企業の規模や導入方法によって異なる可能性があります。
また、これらの事例が示すのは、以下施策の選定から実装までのリードタイムが大幅に短縮されるということです。
- 国際・国内ガイドラインに基づくKPI設定
- 複数施策の費用対効果の比較
- 経営層による定期的なデータレビューの3点を押さえる
ヨガ導入によるメンタルヘルス改善の効果

ヨガがストレス軽減に与える影響
ヨガがストレスを和らげる仕組みは、大きく三つの生理学的メカニズムに集約できます。
- 1. コルチゾール抑制による自律神経の安定
- ヨガの呼吸法とポーズは、副交感神経を優位にし、交感神経の過剰な活動を抑える働きがあります。これにより、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制され、心身がリラックス状態へと導かれます。特にハタヨガなど、呼吸瞑想を重視したプログラムでは、動作中心のヨガよりもコルチゾール低減率が高いと報告されています。参考:ヨガとストレスホルモンの関係|日本ヨガメディカル協会 参考:ホットヨガスタジオLAVAのプログラムを見る
- 2. GABA分泌促進による不安感の軽減
- ヨガの実践により、脳内の抑制系神経伝達物質「GABA(γ-アミノ酪酸)」の分泌が促進されます。GABAは不安感を和らげ、心拍数や血圧の安定にも寄与する物質で、抗不安薬の作用機序にも関係しています。ヨガはこのGABAを自然な形で増やす手段として注目されています。参考:ヨガが自律神経を整える仕組み|yoi(集英社)
- 3. セロトニン経路を介したリラクゼーション反射
- ヨガで筋肉をゆっくり伸ばすと、筋肉の中のセンサー(筋紡錘)が反応し、脳にリラックスの信号が送られます。これにより「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンが分泌され、心の安定や幸福感が高まり、短時間のセッションでも「頭がスッキリした」「肩のこわばりが取れた」といった主観的な変化を実感しやすくなります。参考:ヨガの効果と脳の関係|日本ヨガメディカル協会
ヨガ導入による健康経営の定量的成果:LAVA法人向けサービスの成功事例
企業の健康経営施策として「ヨガ導入」が注目される中、ホットヨガスタジオLAVAが提供する法人向けサービスは、従業員の心身の健康改善において定量的な成果を挙げています。特に、継続的なヨガプログラムの実施が、メンタル・フィジカル両面において高い効果をもたらすことが調査結果から明らかになっています。
導入企業と業種
LAVAの法人向けヨガプログラムは、以下のような多様な業種で導入されています。
- 株式会社SCREENホールディングス(電気機器)
- 株式会社東京建物アメニティサポート(マンション管理業)
- 勤次郎株式会社(システム開発)
- 国分グループ(食品卸売業)
- 株式会社トーシンパートナーズホールディングス(不動産業)
定量的成果と改善率
導入企業の社内アンケートやストレスチェック結果から、以下のような定量的な改善が報告されています。
- 肩こり・腰痛の改善:72%の従業員が「改善を実感した」と回答
- 睡眠の質向上:導入前と比較して満足度が1.4倍に向上
- ストレス指標の改善:高ストレス者の割合が平均で18%減少
- 従業員満足度の向上:福利厚生としてのヨガ導入に対し、85%以上が「満足」と回答
調査結果から見る継続的ヨガの効果
LAVAが実施した「健康経営イベント実施回数に関する調査」によると、年4回以上の継続的なヨガプログラムを導入した企業では、以下のような効果が確認されています。
- ストレスへの効果実感者:単発企画では47%、継続企画では87%(約1.85倍)
- 頭痛・肩こり・腰痛への効果実感者:単発企画では45%、継続企画では65%(約1.44倍)
この調査結果は、継続的なヨガの実施がメンタルヘルスとフィジカルヘルスの両面において、効果実感者を大幅に増加させることを示しています。

提供プログラムの特徴
LAVAでは、企業の課題に応じて以下のようなプログラムをカスタマイズ提供しています。
- ▼ 健康経営プログラム:セミナー30分・ヨガ40分で構成
- セミナーで学び、ヨガで体感。働く人の健康を即サポートするLAVAのプログラムは、企業ごとの課題に合わせて柔軟に提案可能です。
- ▼ 選べる二つの健康増進コンテンツ
- 課題別に選べるオーダーメイドレッスンと、130本以上の動画が見放題の「おうちdeLAVA」で、働く人の健康を即サポート&習慣化。肩こり・腰痛・ストレス・睡眠・メタボ改善まで、企業の健康課題に合わせて柔軟に対応します。
健康経営への貢献
傷病手当金と併用可能な支援制度
企業の健康経営において、うつ病などで休職中の社員を制度的・経済的に支える仕組みの整備は重要です。本記事では、代表的な3つの公的支援制度とその家計インパクト、製造業S社の実践プロセスと導入効果を紹介します。
3つの公的支援制度
- ①精神障害者保健福祉手帳
-
取得条件:医師の診断書と過去6か月の症状記録を提出参考:休職中に活用できる社会保障制度を理解しよう
主なメリット:公共交通機関の運賃割引、所得税の障害者控除(27万円)
申請先:市区町村の福祉課 - ②自立支援医療(精神通院医療)
-
制度概要:心療内科・精神科の医療費自己負担を原則1割に軽減参考:自立支援医療制度の概要
申請書類:医師意見書、通院医療費明細、健康保険証の写し
申請先:市区町村の障害福祉窓口 - ③傷病手当金の延長給付
-
対象:支給開始から1年6か月を超えても就労不能が続く場合参考:自立支援医療(精神通院医療)の概要
延長期間:最長18か月
申請条件:医師の診断書を添えて健康保険組合に申請
注意点:失業給付や障害年金との重複受給は不可 - 制度併用による家計インパクト(試算例)
-
- 平均標準報酬月額30万円の社員が休職6か月目に突入
- 傷病手当金:月約20万円支給
- 自立支援医療で医療費が月2万円 → 4,000円に圧縮(年間約19万円節約)
- 精神障害者保健福祉手帳2級で所得税・住民税が計9万円軽減
- 実質手取りが約14%改善
- 社会保険料の等級変更により、会社負担分含め年間24万円削減効果
- 制度活用の実践プロセス(製造業S社の事例)
-
参考:産業医クラウド
- ・人事担当が傷病手当金申請書と支援制度一覧を本人に配布
- ・産業医が診断書と意見書を同時発行し、通院回数を最小化
- ・社労士が提出書類をチェックし、翌営業日までに差し戻し対応
- ・人事が給付決定後の税制優遇や保険料変更を給与システムに反映
- 導入効果(製造業S社の実績)
-
参考:厚生労働省 メンタルヘルス対策の取組事例集
- 休職者30名中22名が支援制度を併用
- 医療費自己負担:平均68%削減
- 療養期間:9.2か月 → 7.4か月に短縮
- 早期復職率:15ポイント向上
- 保険料負担回避額:約480万円
- 従業員満足度:「安心して治療に専念できた」82%
休職者への支援制度とヨガの役割

休職制度の概要と課題
休職制度は、労働基準法が定める解雇制限や安全配慮義務を土台に、各企業の就業規則で具体的な運用ルールを定める仕組みです。
法令自体は休職を直接義務付けていませんが、私傷病休職規程として多くの企業が独自の条項を設け、従業員を一定期間保護する枠組みを整えています。
標準的な休職期間は勤続年数に応じて3か月〜2年程度が目安とされ、フローは「有給休暇消化 → 診断書提出 → 会社が休職命令→定期報告→復職判定」という段階を踏むケースが大半です。
メンタル不調者に関しては、復職判断の難易度が身体疾患より格段に高い点が大きな課題になっています。独立行政法人労働者健康安全機構が発表した2023年統計によると、うつ病で休職した社員の再休職率は1年以内に34%、2年以内に47%と半数近くが職場に定着できていません。また、復職可否を巡る医師と産業医の見解相違が約23%の企業で報告されており、判断基準の統一も急務とされています。
参考:適切な復職判定の原理原則や主治医との連携とは?制度を運用する現場には複数のボトルネックが潜んでいます。
人事担当者からは「診断書提出が休職開始後2週間も遅れ、手続きが後ろ倒しになった」という声、ラインマネジャーからは「チーム体制を急に組み替える負荷が大きく、部下への説明に苦慮した」という声が聞かれます。さらに同僚側には「復職時にどの程度業務を割り当てていいのか不安でコミュニケーションがぎこちなくなる」という心理的影響も残ります。こうした人間面の負担は制度文書だけではカバーしきれず、サポート体制の再設計が求められています。
チェックリストで自社制度を棚卸ししてみましょう。
- □ 就業規則に休職の定義・期間・延長条件が明記されているか
- □ 精神科医・産業医との情報共有フローが週次以上の頻度で確立しているか
- □ 休職者の業務棚卸しリストと引継ぎ手順書を標準化しているか
- □ 復職判定会議に人事・産業医・上司・労組が参画する形式を採用しているか
- □ 同僚向けガイドラインやEAP(従業員支援プログラム)の告知が行き届いているか
これらに×が付く項目が多い場合、制度そのものが形骸化している可能性があります。ヨガやマインドフルネスといったリワーク支援を組み込み、運用プロセスをアップデートすることで、休職 → 復職のサイクルをより実効的に回せるようになります。
ヨガを活用したリワークプログラム
メンタルヘルス不調による休職者の復職支援策として、ヨガを取り入れたリワークプログラムが注目されています。
復職プロセスを「休職中」「試験出社」「本格復職」の三段階に分け、それぞれに適したヨガセッションを組み込むことで、心身の安定と職場復帰の成功率向上が期待されます。
- 各フェーズのヨガ活用法
-
- 休職中:週2回30分のリストラティブヨガ(オンライン)で不安定な自律神経を整える。
- 試験出社:短時間勤務の前後に15分の呼吸法中心のオフィスヨガを実施し、仕事と休息の切り替えを支援。
- 本格復職前:昼休みに30分のパワーヨガを導入し、集中力と持久力の回復を促進。
- 効果測定と成果
-
- 生理指標:Oura Ringによる心拍変動(RMSSD)が平均33 → 46msに改善。
- 睡眠の質:深い睡眠時間が1.1 → 1.6時間に増加。
- 心理指標:POMS2「疲労‐緊張」尺度が18%減少。
- 復職率:6ヶ月後の復職率が92%に達し、従来型(78%)を大きく上回る。
参加者からは「生産性が落ちなかった」「通院日でも受講できた」などの好意的な声が寄せられ、社内報で共有することで信頼感と自発的な参加が促進されました。
参考:リワークプログラムの実態とその長期的効果に関する文献レビュー(東京大学) 参考:現代ヨガの肯定的効果に関する実践的研究(甲賀看護専門学校)会社が取り組むべき健康経営の具体策

健康経営優良法人を目指すための施策
健康経営優良法人認定制度は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する表彰制度です。企業の健康経営の取り組みを「見える化」し、社会的評価や採用力の向上につなげることを目的としています。
参考:経済産業省「健康経営優良法人認定制度」2024年度の評価項目は、以下の5つの大項目に整理されています。
- 経営理念・方針
- 組織体制
- 制度・施策実行
- 評価・改善
- 法令遵守・リスクマネジメント
このうち「制度・施策実行」領域では、メンタルヘルス関連の取り組みが複数項目にわたって評価対象となっており、特に「ストレスチェック後の職場環境改善」が重要な評価ポイントです。単なる法定対応にとどまらず、改善アクションまで踏み込むことが求められます。
自社の現状把握と改善ステップ
まずは、経済産業省が公開しているスコアリングシートを活用し、以下のように自己評価を行います。
- 「○」:基準を満たしている
- 「△」:一部実施している
- 「×」:未実施
この評価結果をレーダーチャートに落とし込むことで、弱点領域が一目で把握できます。
次のステップは、未実施項目のうち経営インパクトが大きく、実装コストが比較的低いものから優先順位を付けることです。
たとえば「ラインケア研修」は外部講師派遣費用が年間50万円程度で済む一方、メンタル不調の早期発見率が向上した事例もあり、投資対効果が高い項目として着手しやすいといえます。
優先改善項目が定まったら、ヨガ導入を核とする3カ年ロードマップを設計します。
- 初年度:
- 週1回のオフィスヨガを開始。予算はインストラクター派遣費・会議室転用費を合わせて年間120万円。KPIは参加率30%とストレス自己評価スコア5%改善。責任者は人事部ウェルビーイング担当マネジャー。
- 2年目:
- 在宅勤務社員向けにオンラインクラスを追加。参加率を50%へ拡大し、ストレス関連休業日数10%削減を目標に設定。
- 3年目:
- EAP(従業員支援プログラム)や睡眠セミナーと統合した包括プログラムへ発展。欠勤・プレゼンティーズムを含む総医療コストを15%削減することをKPIとし、経営企画部がROI計算を担当して経営陣へ四半期ごとに報告。
認定取得後のメリットとしては、企業ブランディングや採用力向上が挙げられます。民間調査では、認定取得企業の株価や採用エントリー数が向上した事例も報告されており、健康経営施策への追加投資を引き出す材料となります。
健康経営支えるヨガの力

LAVA法人サービスで実現する、持続可能なウェルビーイング
従業員の心身の健康は、企業の生産性・定着率・ブランド力に直結します。
LAVAの法人向けヨガサービスは、健康経営を推進する企業に向けて、出張・オンラインヨガサービス、LAVA法人会員サービスの2形態でヨガプログラムを提供し、従業員のウェルビーイング向上を支援しています。
LAVA法人サービスの2つの柱
- ①出張・オンラインヨガサービス
- ・インストラクターが企業へ訪問し、会議室などでヨガを実施(オンライン・ハイブリット・スタジオ貸切開催も可能)
- ・1回15分~60分、参加人数上限なし、(オンラインは300名まで対応)
- ・ヨガマット・イベント備品レンタルも可能
- ・肩こり・腰痛・女性支援・ストレスケアなど、目的別プログラムを提供
- ②スタジオ法人会員
- ・全国590店舗のLAVAスタジオを優待価格で利用可能
- ・従業員が自分のペースで通える柔軟な仕組み
- ・育児・介護中の社員にも好評
健康経営への貢献
LAVAのヨガサービスは、以下のような健康経営指標の改善に寄与します。
- 定量的な効果
-
- 欠勤率の低下
- 離職率の改善
- プレゼンティーズム(出勤しているが生産性が低い状態)の解消
- 医療費・保険料の削減
- 定性的な効果
-
- 従業員満足度の向上
- 心理的安全性の確保
- 社内コミュニケーションの活性化
- 健康経営優良法人認定の取得支援
導入企業の声(一部抜粋)
- 「従業員の健康意識が高まり、社内の雰囲気が明るくなった」
- 「育児中の社員が在宅で参加できる点が好評」
- 「健康経営の取り組みとして、IR資料にも活用できた」
- 「採用活動で“ホワイト企業”としての印象が強まり、応募数が増加した」
導入ステップ
- ヒアリング・課題整理
- プログラム設計(目的別・対象者別)
- 実施(出張/オンライン/スタジオ)
- 効果測定(定量・定性指標)
- 改善提案・継続支援
ヨガは「福利厚生」から「経営戦略」へ
まとめ:ヨガ導入によるメンタルヘルスケアの未来

メンタルヘルスケアの進化と会社の役割
働き方改革やDXの進展、そしてパンデミックを経て、企業におけるメンタルヘルス対策は「労務管理」から「経営戦略」へと進化しました。
現在では、有価証券報告書での人的資本開示や、ストレスチェック結果のIR開示など、心の健康が企業価値に直結する時代です。
AIやVRなどのテクノロジーが進化する一方で、ヨガは「身体と呼吸」によるアナログな体験として、デジタル疲労を癒す手段として再評価されています。
ヨガを活用した健康経営の可能性
ヨガ導入により、傷病手当金の削減や離職率の低下、エンゲージメント向上といった成果が報告されています。Sustainalyticsの調査では、人的資本への投資が多い企業は株価パフォーマンスが年率3〜4%上振れする傾向も確認されています。
参考:KIWI GO「健康経営とESGの関係」- 実践に向けた5ステップ
-
- ストレスチェックと欠勤データを確認
- 経営層向けの導入効果資料を作成
- 週1回×3ヶ月のパイロット実施
- マインドフルイーティングやウェアラブル連携も検証
- 成果を社内で共有し、次年度予算化へ
- 結論
- ヨガを軸にした健康経営は、従業員の幸福と企業の成長を両立させる戦略的施策です。今こそ、自社に合った形でヨガを取り入れ、「健康が競争力になる」未来を実現しましょう。