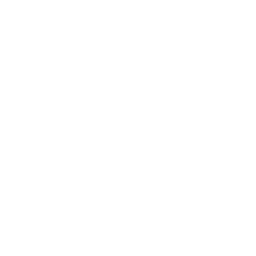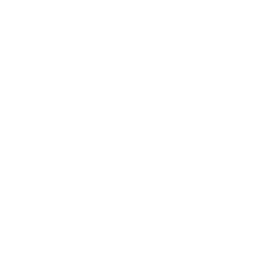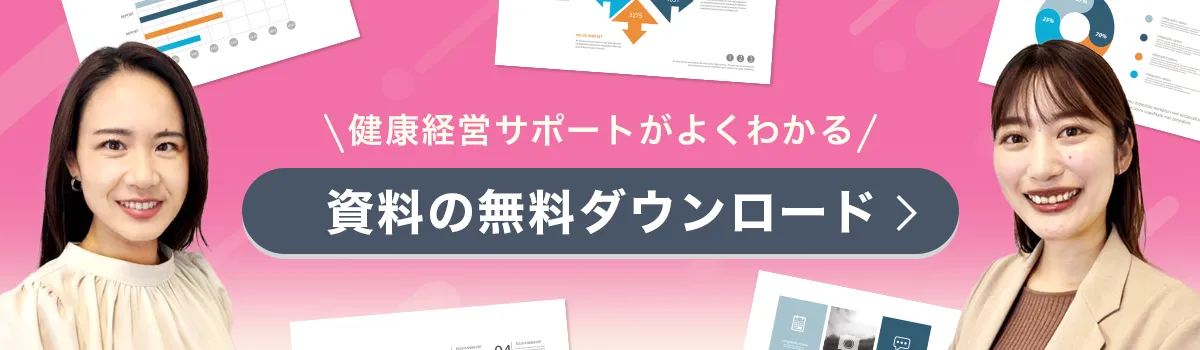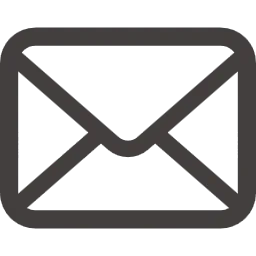【国の取り組み】医療費削減と健康寿命延伸の両立:できること5つをご紹介

健康保険組合における医療費削減と健康寿命延伸の両立を目指す5つの取り組みを本コラムで紹介いたします。紹介する取り組みは急速な高齢化が進む中で、持続可能な医療費削減と国民の健康維持を同時に実現するために非常に重要です。それぞれの方法がどのように医療費の削減と健康寿命の延伸に寄与するのか本コラムにてご確認ください。
日本の医療費の現状と増加要因

日本の医療費は年々増加しており、その背景には複数の要因が関与しています。これらの要因がどのように医療費の増加に寄与しているのか、また今後の予測や懸念事項についても記載いたします。
医療費の年々の増加
近年、日本の医療費は年々増加傾向にあります。2021年度には総医療費が45兆359億円に達し、これは前年度比で約2.2%の増加を示しています。今後、団塊の世代が75歳以上となる2025年にはさらに医療費の増加が懸念されています。
この医療費増加の主な要因として、高齢化と慢性疾患の増加が挙げられます。高齢化に伴い、65歳以上の医療費が全体の約60.6%を占めるようになり、慢性的な疾病の治療費も増加しています。これにより、医療保険制度への負担が大きくなり、社会全体の財政にも影響を及ぼしています。
以下の表は、過去5年間の日本の医療費の推移を示しています。
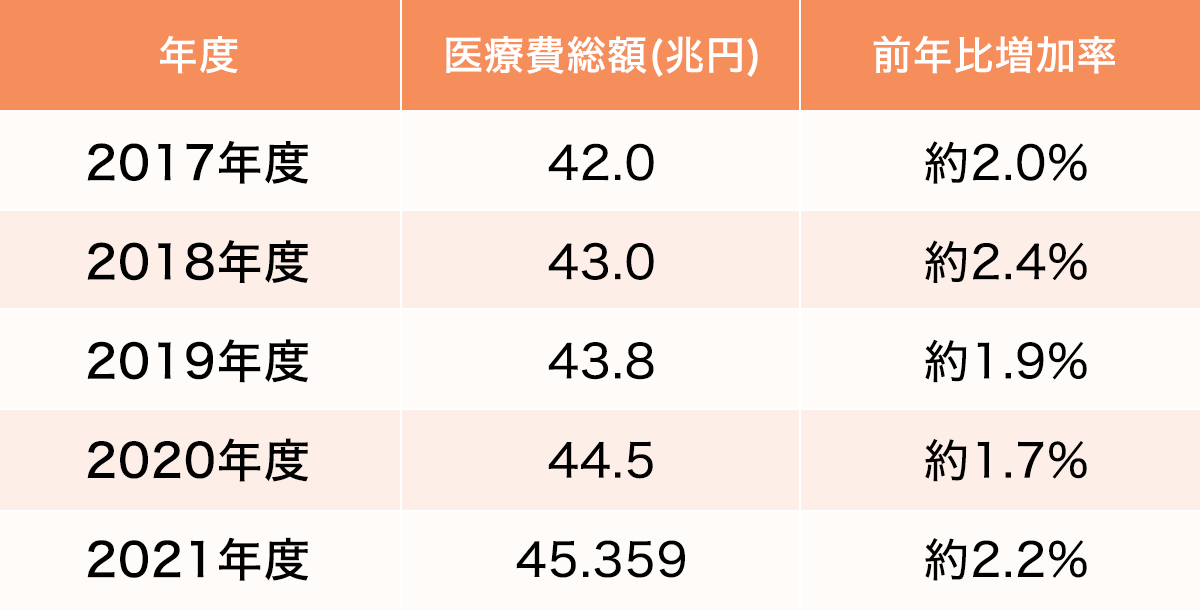
この医療費の増加には、高齢者特有の医療サービスや治療に高コストなものが多いのも一つの理由になります。例えば、長期的な慢性疾患の管理や介護が必要なケースでは、医療費だけでなく介護費用も併せて必要となります。また、先進医療技術や特殊な治療法の利用も高齢者医療費の増加要因となっています。これらの要因を踏まえ、効果的な医療費削減策と健康寿命延伸の施策が緊急に求められています。
医療技術の高度化とはしご受診
医療技術の進歩により、今ではさまざまな病気やけがに対して多くの治療法が選べるようになりました。これにより、患者がより良い治療を求めて同じ症状で複数の病院や診療所を受診するはしご受診が増えています。
はしご受診が増えると、同じ検査や治療が何度も行われることになり、医療費が増加します。また、新しい医療技術を使う治療は高額になることが多く、医療費の増加に影響します。
特定健診の未受診や結果の放置
特定健診の未受診や健診結果の放置は、医療費の増加に大きく寄与しています。特定健診は生活習慣病の早期発見と予防を目的としており、その重要性は非常に高いものです。
未受診や結果の放置がもたらす健康リスクには、疾病の早期発見が遅れることや、適切な治療が開始されないことなどが含まれます。これにより、病状が進行し、最終的には高額な医療費が必要となるケースが増加します。
医療費削減に向けた5つの取り組み【2025年最新】
取り組み①特定健診と特定保健指導の実施率向上

医療費削減と健康寿命延伸を実現するための第一のアプローチとして、特定健診と特定保健指導の実施率向上に焦点を当てます。これにより、早期の健康リスクの発見と適切な指導が可能となり、長期的な医療費の抑制と加入者の健康寿命の延伸が期待されます。
健診の重要性と実施率の現状
特定健診は、早期に生活習慣病のリスクを発見し、適切な対策を講じることが可能です。これにより、重大な健康問題の予防や、治療にかかるコストの削減につながります。また、定期的な健診を通じて自身の健康状態を把握することで、個人の健康管理意識の向上が期待され、結果として健康寿命の延伸に寄与します。
特定健診の実施率は2018年度には55%だったが、2023年度には60%に達しています。過去5年間で緩やかな増加傾向にありますが、依然として多くの加入者が健診を受けていない現状があります。
特定健診の実施率が低い主な原因としては
・受診の手間や時間的な負担
・健診結果に対する不安感
・健診の必要性に対する認識不足
が挙げられます。
また、職場環境や個人の生活習慣によって、定期的な健診を受けることが難しい場合も多いです。これらの課題を解決するためには、より利用しやすい健診環境の整備や、健診の重要性を再認識させるための継続的な啓発活動が必要とされています。
実施率向上のための取り組み
特定健診と特定保健指導の実施率向上のための取り組みの一例を以下に紹介いたします。
・政府や健康保険組合による施策:インセンティブの提供や啓発活動を通じて、健診の実施率を高めます。
【事例:SUMIグループ健康保険組合(旧:ベンチャーバンク健康保険組合)】健康診断をしたら、インセンティブポイントが付与される。早期受診を促すために期初受診の方へのポイント付与数を多く設定している。
参考:SUMIグループ健康保険組合 (旧:ベンチャーバンク健康保険組合)・テクノロジーの活用:リマインダーやオンライン予約システムなどの最新技術を導入し、参加者の利便性を向上させます。
・企業やコミュニティとの連携事例:職場や地域社会と協力し、健診の重要性を広める取り組みを推進します。
取り組み②データヘルスの活用
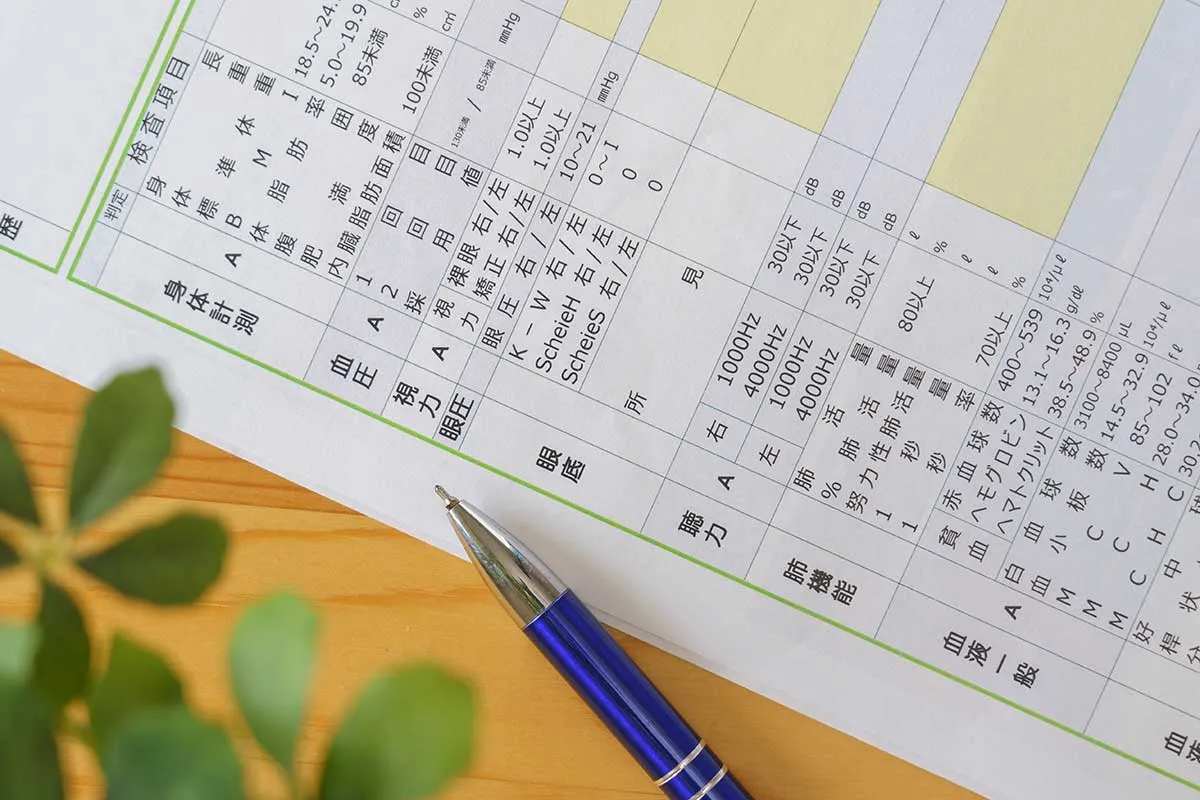
第二のアプローチは、データヘルスの活用です。医療費削減や健康寿命延伸における具体的な活用方法等を紹介します。
データヘルスとは
データヘルスとは、健康に関連するデータの収集、分析、および活用を指します。これには、ウェアラブルデバイスや健康管理アプリから得られる個人の健康データ、医療機関での診療記録、さらには公衆衛生データなどが含まれます。データの分析により、個々の健康リスクを早期に特定したり、予防医療の効果を高めたりすることが可能です。また、医療リソースの最適化や、個別化された治療計画の策定にも役立ちます。
他の健康管理手法と比較すると、データヘルスはより科学的根拠に基づいたアプローチを提供します。従来の健康管理が主に経験や直感に頼るのに対し、データヘルスは具体的なデータに基づいて意思決定を行うため、より精度の高い健康管理が実現できます。
活用事例
データヘルスの活用事例として、自治体や企業での具体的な取り組みが挙げられます。以下にいくつかの実際の導入事例を紹介します。
・広島県呉市
概要:広島県呉市は診療報酬明細書データを独自の技術で分析し、効率的・効果的な保健事業の実施に必要な情報を提供するサービスを実施。
参考:総務省Webサイト・三菱自動車健康保険組合
概要:健康保険組合が配布するウェアラブルウォッチにて歩数を把握。ウォーキング歩数に応じて健保ポイントを付与。
参考:ウェアラブルウォッチこれらの事例から、データヘルスの活用により医療費削減と健康改善が実現可能であることが示されています。成功には適切なデータ管理と、関係者間の協力が不可欠である一方、プライバシー保護や初期導入コストといった課題も存在します。これらを克服するための具体的な対策が今後の展開において重要となります。
取り組み③ジェネリック医薬品の普及促進

ジェネリック医薬品の普及促進が医療費削減にどのように貢献できるかを説明いたします。
ジェネリック医薬品のメリット
・コスト削減効果
ジェネリック医薬品は、ブランド薬に比べて開発コストが低いため、価格も抑えられます。これにより、医療費全体の削減が可能となります。
・医療アクセスの向上
ジェネリック薬の低価格化により、患者は必要な薬を手軽に入手できるようになります。これにより、治療を継続しやすくなり、健康管理が向上します。
・環境や社会へのポジティブな影響
ジェネリック薬の普及は、薬の製造過程での資源使用の効率化や、余剰薬の廃棄削減にも寄与します。これにより、持続可能な社会の実現に向けた一助となります。
普及促進のための政策
・政府の補助金やインセンティブ制度
ジェネリック医薬品の開発および製造を支援するために、政府は補助金や税制上の優遇措置を提供しています。これにより、製薬会社がジェネリック医薬品の市場投入を増やすことが期待されています。
・教育・啓発活動の取り組み
医療従事者や患者に対して、ジェネリック医薬品の有効性や安全性についての正しい情報を提供するための教育プログラムや啓発キャンペーンが実施されています。これにより、ジェネリック医薬品への信頼と利用率の向上を図っています。
・規制緩和や市場参入の支援策
ジェネリック医薬品の市場参入を容易にするために、承認プロセスの簡素化や迅速化が進められています。また、新規参入企業への支援策も講じられ、競争の促進と価格の低下を目指しています。
取り組み④セルフメディケーションの推進

セルフメディケーションの推進は、医療費削減と健康寿命延伸を実現するための重要なアプローチです。セルフメディケーションが医療費削減や健康寿命延伸にどのように寄与するかを紹介します。
セルフメディケーションとは
セルフメディケーションとは、個人が自身の健康状態や症状に基づき、医師の診断や処方箋なしで医薬品を使用し、健康管理を行うことを指します。このアプローチは、自己判断による健康管理として、軽度の症状に対する迅速な対応や、日常的な健康維持に寄与します。
セルフメディケーションの推進は、医療システム全体において医療費の削減や医療資源の効率的な活用を促進するだけでなく、個人および社会における健康意識の向上や生活の質の改善にも繋がります。これにより、健康寿命の延伸や持続可能な医療保険制度の維持が期待されます。
推進のための施策
セルフメディケーションを推進するためには、以下の対策が必要です。
・教育・啓発プログラムの実施
加入者に対して健康管理の知識を提供し、適切なセルフメディケーションの方法を伝える。
・必要な法整備やガイドラインの策定
セルフメディケーションの安全性を確保するための法的枠組みやガイドラインを整備する。
・テクノロジーの活用
健康管理アプリなどのデジタルツールを活用し、加入者が効果的にセルフメディケーションを行えるよう支援する。
成功事例とその影響
セルフメディケーションの推進に成功した事例は数多く存在します。
具体例・オーストラリア
地域コミュニティと連携し、自己管理プログラムを導入することで、加入者の健康意識を高める取り組みが行われています。自己管理プログラムにより慢性疾患の管理が向上し、医療費が約20%削減されました。
・三菱商事健康保険組合
菱商事健康保険組合は、事業主と複数の健康保険組合と連携してセルフメディケーション保健事業を推進しています。データ分析に基づいた啓発活動や薬剤師の介入を通じて、組合員の健康意識を向上させています。医療機関への対面受診のみに依存しない健康管理が促進され、医療費の削減と健康維持に成功しています。
参考:事業名:コラボヘルスで推進するセルフメディケーション推進事業これらの事例は、他の地域や組織に対して貴重な示唆を提供しています。まず、セルフメディケーションの成功にはテクノロジーの効果的な活用が不可欠であり、適切なツールの導入が健康管理の支援を強化します。また、地域社会との連携や継続的な教育・啓発活動が、加入者の積極的な健康管理を促進する鍵となります。これらの要素を取り入れることで、他の組織や地域でも同様の成果を期待することが可能です。
取り組み⑤スポーツを通じた健康増進

5つ目のアプローチとして、スポーツを通じた健康増進が挙げられます。スポーツ活動を促進することで、国民の健康意識の向上と医療費の抑制を目指します。
スポーツと健康の関係
スポーツは、身体的だけではなく、精神的健康の向上や社会に大きく寄与します。
定期的な運動をすると以下効果を得ることが出来ます。
身体的効果
・心肺機能の強化
・筋力の増加
・柔軟性の向上
・生活習慣病の予防や管理
・肥満防止
精神的効果
・ストレスの軽減
・気分の改善に効果
・うつ症状の緩和
・達成感や自己効力感の向上
社会的効果
・個人間のコミュニケーション促進
・協力や相互理解の深化
・地域社会の絆の強化
・社会全体の健康増進
スポーツ庁の取り組み
日本のスポーツ庁は、スポーツを通じた健康増進を推進するために、基本方針として健康寿命の延伸と医療費削減の両立を目指しています。これに基づき、国民のスポーツ参加率の向上や、地域スポーツクラブの支援など、具体的な目標を設定しています。
具体的なプロジェクトとしては、「スポーツで健康プロジェクト」が挙げられます。このプロジェクトでは、地域コミュニティと連携し、定期的なスポーツイベントを開催することで住民の健康促進を図っています。また、「高校スポーツ支援プログラム」では、若年層の健康意識を高め、持続的なスポーツ活動の継続を支援しています。
これらの取り組みによって、国民の健康寿命の延伸が期待されており、結果として医療費の抑制にも寄与することが見込まれています。スポーツ活動を通じて、身体的・精神的な健康が向上し、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に向けた基盤が強化されることが期待されています。
スポーツを継続することの効果
スポーツを継続的に行うことは、長期的な身体機能の維持や向上に寄与します。定期的な運動により筋力や柔軟性が保たれ、年齢とともに低下しがちな身体能力を効果的に維持することが可能です。また、スポーツは心肺機能の強化にもつながり、全体的な体力の向上を促進します。
さらに、スポーツは生活習慣病の予防と改善において重要な役割を果たします。定期的な運動は肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病のリスクを低減し、既に患っている場合でも症状の改善に寄与します。これにより、医療費の削減や健康寿命の延伸につながります。
加えて、スポーツは社会的および精神的なメリットも提供します。チームスポーツや定期的な運動活動は、コミュニティとのつながりを深め、孤独感の減少やメンタルヘルスの向上に寄与します。さらに、目標達成や競争を通じて自己肯定感を高めることができ、全体的な生活の質の向上につながります。
民間サービスとの連携で運動習慣を支援する事例
ホットヨガスタジオLAVA

ご利用者様の80%以上が未経験でスタートし、全国540店舗以上の利便性の高い店舗の中からお好きな店舗をご利用いただけます。※1
お好きなタイミングでご利用いただけるので、多くの方が長くご愛顧くださいます。
また、直接雇用のインストラクターが直接指導するので、98%のお客様が効果を実感されています。※2
効果を体感できる事は継続のモチベーションにつながります。
組合員様・従業員様の運動習慣の増進で医療費削減にお役立てください。
まとめ
・特定健診と特定保健指導の実施率向上により、早期の健康リスク発見と適切な指導が可能となり、長期的な医療費抑制と健康寿命延伸が期待される
・データヘルスの活用で個々の健康リスクを早期に特定し、予防医療の効果を高めることができる
・ジェネリック医薬品の普及促進により、医療費全体の削減と医療アクセスの向上が図れる
・セルフメディケーションの推進は、医療費削減と健康意識の向上に寄与する
・スポーツを通じた健康増進は、身体的・精神的健康の向上と医療費抑制に効果的
できる事から取り組んで、医療費削減につなげていただければと存じます。