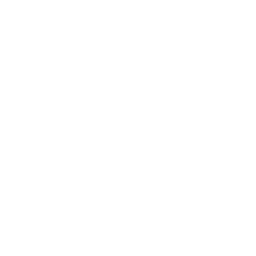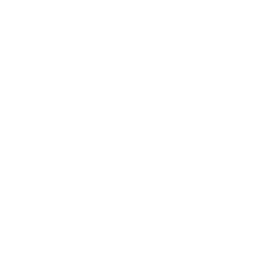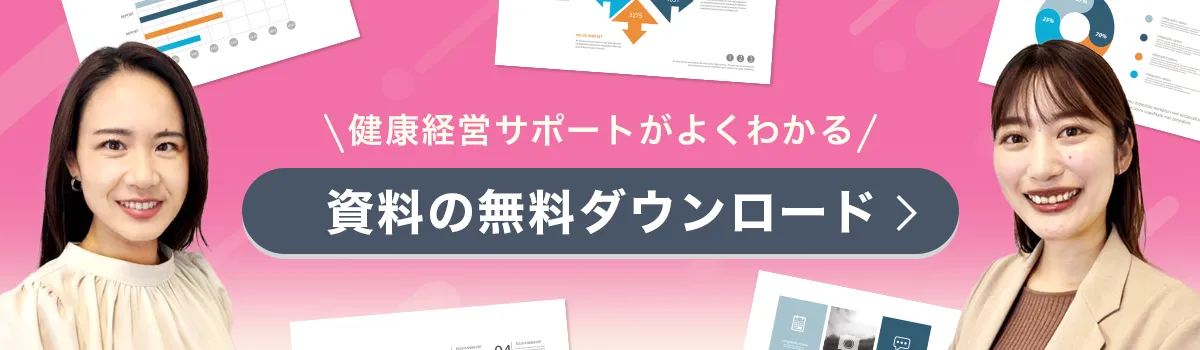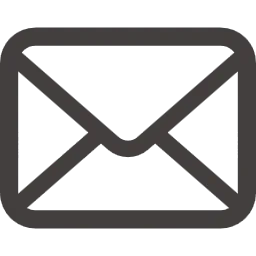【企業・健保担当者向け】フレイル予防の食事と運動:企業の健康管理部門が押さえるべきポイント

少子高齢化が進む日本では、高年労働者の健康と安全がますます重要な課題となっています。厚生労働省は、フレイル対策を推進し、健康寿命の延伸を目指しています。企業の保険事業や健康経営担当者にとって、フレイル予防は生産性向上や人材確保に直結する大切な要素です。
従業員の健康を守り、活力ある職場環境を維持するために、企業がフレイル予防に積極的に取り組むことが重要です。これにより、従業員の健康寿命を延ばし、業績向上にもつながるでしょう。
フレイルの評価方法_Friedの5項目基準

Friedの5項目基準は、フレイル(虚弱)の診断において広く認知されている評価方法です。この基準は、以下の5つの項目を基にしており、従業員の健康状態を体系的に評価するために有効です。
・体重減少: 過去12か月間に意図せずに体重が5kg以上減少した場合。
・筋力低下: 握力測定や椅子からの立ち上がりテストで基準値を下回った場合。
・疲労感: 日常的な活動に対して持続的な疲労感を感じている場合。
・歩行速度の遅さ: 4メートル歩行テストで基準値以下の速度の場合。
・低身体活動: 週間を通じて身体活動量が極端に低い場合。
これらの基準を用いることで、フレイルの早期発見が可能となります。企業の健康管理部門は、定期的な健康チェックやフィジカルテストの実施を通じて、従業員のフレイルリスクを評価することができます。
フレイルの評価方法_Frailty Index

Frailty Indexは、フレイルの評価に用いられる包括的な指標であり、個々の健康状態を多面的に捉えることができます。慢性的な疾患、身体的機能の低下、精神的健康状態、社会的支援の有無など複数の健康要因や疾患の有無を総合的に評価することで、個人の脆弱性や健康リスクを定量化します。この指標は、フレイルの段階的な評価や個別の予防策の立案に役立ち、企業の健康管理部門において従業員の健康維持・増進に貢献します
【Frailty IndexとFriedの5項目基準との違い】
評価の範囲と詳細さにあります。
Friedの5項目基準
主に身体的側面に焦点を当てています。
Frailty Index
身体的、精神的、社会的な要素を総合的に評価します。
これにより、Frailty Indexはフレイルのより包括的な理解を提供し、Friedの基準と併用することで、より精度の高い健康評価が可能となります。
フレイルの原因と症状

身体的フレイル
身体的フレイルは、高齢者における身体機能の低下を特徴とするフレイルの一形態であり、筋力低下、体重減少、歩行速度の遅さなどが主な症状として現れます。これらの症状は、従業員の健康状態に直接的な影響を与えるだけでなく、業務遂行能力や生活の質にも深刻な影響を及ぼします。
具体例
1 筋力低下
日常生活における動作の制限や転倒リスクの増加につながります。筋力が低下すると、物の持ち運びや階段の上り下りといった基本的な動作が困難になり、業務効率の低下を招く可能性があります。
2 体重減少
筋肉量の減少や栄養不足を示す重要な指標です。体重が減少すると、免疫機能の低下や骨密度の減少が引き起こされ、骨折や感染症のリスクが高まります。また、体力の低下は持続的な業務遂行を困難にし、休職や早期退職の原因となることもあります。
3 歩行速度の遅さ
移動能力の低下を示し、職場内での迅速な対応や緊急時の避難行動に支障をきたす可能性があります。歩行速度の低下はまた、全身の血流不足や心肺機能の低下とも関連しており、全体的な健康状態の悪化を示唆します。
企業の取り組み例
1 筋力トレーニングや有酸素運動
従業員の筋力維持と体力向上を図ります。例えば、週に数回のフィットネスセッションやストレッチクラスの提供が考えられます。運動量が程よいフィットネスの一例としてヨガがあげられます。ホットヨガスタジオLAVAでは法人向けサービススタジオプランがあり、従業員の筋力維持と体力向上の為と多くの企業や健康保険組合が導入しています。
2 栄養サポート
バランスの取れた食事を促進するための食事指導や栄養補助食品の提供を行います。特に、たんぱく質やビタミンD、カルシウムの摂取を重視します。
ビタミンDは日光浴でも得られます。地域や季節などによって差が出てしまいますが、東京の7月(正午)では、1分-30分ほどの日光浴で体内にてビタミンDが合成されます。
3 職場環境の改善
安全で快適な作業環境を整備し、転倒リスクを低減するための措置を講じます。例えば、滑りにくい床材の使用や手すりの設置などが有効です。
これらの取り組みを通じて、企業は従業員の身体的フレイルを効果的に予防・改善し、健康的で生産性の高い職場環境を実現することが可能となります。
社会的フレイル
社会的フレイルは、高齢者における社会的な脆弱性を指し、社会的孤立や支援の欠如、社会参加の減少が主な要因となります。これらの要因は、個人の精神的健康や身体的健康に直接的な影響を及ぼし、結果としてフレイル状態を悪化させる可能性があります。
具体例
1 社会的孤立
高齢者が家族や友人との交流を失い、孤独感を感じることで、うつ病や認知機能の低下を招きます。
2 支援の欠如
日常生活に必要な助けが不足し、健康管理や生活の質の維持が困難になる原因となります。
3 社会参加の減少
コミュニティ活動や趣味の追求が制限され、身体的活動の低下や精神的な充実感の欠如を引き起こします。
フレイル予防の為の孤独の解消に向けたイベント事例
株式会社JTB
・目的:シニアのフレイル予防を通じて孤独を解消し、QOLを向上させる。 シニアが定期的に外出したくなるきっかけを提供し、生活スタイルを活性化する。
・概要:近隣の公立小学校で、シニア向けの「学習」「運動」「交流」サービスを提供。 シニアのスキルや経験を学校運営に活かし、承認欲求を満たす。
参考:Re小学校って? - re-primary-school-project企業の取り組み例
1 コミュニケーション促進プログラム
定期的なチームビルディングや社内イベントを開催し、従業員間の交流を深めることで、社会的つながりを強化します。
2 サポートシステムの構築
メンタルヘルスサポートやカウンセリングサービスを提供し、従業員が安心して支援を求められる環境を整備します。
3 社会参加の機会提供
ボランティア活動や趣味のサークルなど、従業員が積極的に参加できる活動を支援し、社会的なつながりを促進します。
このように、企業の健康管理部門が積極的に社会的フレイルの予防・改善に取り組むことで、従業員の健康維持と職場環境の向上に大きく寄与することが可能です。
認知機能の低下

認知機能の低下は、フレイルの進行に深刻な影響を与える要因の一つです。記憶力や判断力の低下は、従業員の日常業務遂行能力に直結し、業務効率の低下やミスの増加を招く可能性があります。また、認知機能の低下は日常生活にも影響を及ぼし、自立した生活を維持することが困難になるため、企業としても早期対応が求められます。
企業が認知機能の低下を早期に発見し、支援するためには、定期的な認知機能評価の実施が重要です。
具体例
・簡易な認知テストの導入
・定期的な健康診断に認知機能の評価項目を追加
・結果に基づいて個別のサポートプログラムを提供
・認知機能の維持・向上を目的とした研修やトレーニングプログラムを導入
企業の取り組み例
1 栄養バランスの改善
宅配食やミールキットサービスを利用して、認知機能低下リスクを低減する栄養素を含むメニューを提供します 。
2 運動プログラムの導入
定期的な運動は認知機能の維持に寄与します。社員が参加できる運動プログラムやフィットネスセッションを提供することで、身体活動を促進し、認知機能の低下を防ぐことができます。
3 メンタルヘルスサポート
社員に対してカウンセリングサービスやストレス管理のワークショップを提供することで、メンタルヘルスを支援し、認知機能の低下を防ぐことができます。
フレイルの影響と予防の必要性
転倒リスクと日常生活能力の低下

フレイルは高齢期における身体的および精神的な衰えを伴い、転倒リスクの増加と日常生活能力の低下を引き起こします。具体的には、筋力低下やバランス感覚の低下が転倒の可能性を高め、これが結果として自立度の低下や要介護状態への移行を促進します。
例えば、日本の高齢者人口の約30%がフレイルの症状を示しており、そのうちの約50%が転倒経験を有するとされています。転倒は骨折や入院を招く要因となり、高額な医療費や介護費用が企業や社会に大きな負担をもたらします。また、転倒による怪我は従業員の労働能力を一時的または永久的に低下させ、職場の生産性にも悪影響を及ぼします。
企業の取り組み例
1 定期的な運動プログラムの導入
筋力とバランスを強化する運動を組み込むことで、転倒リスクを軽減します。
2 職場環境の安全性向上
滑りにくい床材の使用や障害物の除去など、物理的な安全対策を実施します。
3 転倒予防教育の実施
従業員に対して転倒のリスクと予防方法についての教育を行い、意識を高めます。
4 健康診断の強化
早期にフレイルの兆候を発見し、適切な介入を行うための健康診断を定期的に実施します。
これらの対策を通じて、企業は従業員の健康維持と自立支援を促進し、結果として生産性の向上や医療・介護コストの削減につなげることができます。フレイル予防に積極的に取り組むことで、従業員の生活の質を向上させるとともに、企業全体の持続可能な成長を支える基盤を構築することが可能となります。
要介護状態への進行防止

フレイルが進行し要介護状態に移行することは、個人の生活の質の低下のみならず、企業にとっても大きな課題となります。要介護状態に陥ることで従業員の業務遂行能力が著しく低下し、結果として生産性の減少や医療費の増大といった経済的負担が企業にも波及します。したがって、要介護状態への進行防止は、従業員の健康維持と企業の持続的な成長の両面から極めて重要です。
フレイルが要介護状態に進行するプロセスには、身体的な筋力低下や歩行速度の遅さに加え、認知機能の低下や社会的な孤立といった複合的な要因が絡み合っています。この進行を防ぐためには、早期にフレイルの兆候を捉え、適切な介入を行うことが不可欠です。企業は定期的な健康診断を通じて従業員の健康状態をモニタリングし、フレイルの早期発見に努める必要があります。
企業の取り組み例
1 健康増進プログラム導入
筋力トレーニングや有酸素運動、バランス運動を組み合わせた運動プログラムを提供し、従業員の身体機能の維持・向上を図ります。高齢に方も安心して行える人気の健康増進プログラムとして、ヨガが挙げられます。ヨガ業界最大手のホットヨガスタジオLAVAでは健康増進プログラムという、出張型のレッスン提供もされています。
2 栄養指導
バランスの取れた食事を推奨し、特にたんぱく質やビタミンD、カルシウムの適切な摂取をサポートする食事プランを提供します。
3 メンタルヘルスサポート
認知機能の低下や社会的孤立を防ぐために、カウンセリングサービスや社内コミュニティ活動を促進します。
4 定期的な健康チェック
フレイルの進行を早期に発見するために、定期的な健康診断とフォローアップを実施します。
これらの施策を通じて、企業は従業員の健康状態を効果的に維持・改善し、要介護状態への進行防止を実現することが可能です。従業員一人ひとりが健康で活力ある生活を送ることは、企業全体の生産性向上と持続可能な成長に直結します。
食事によるフレイル予防
たんぱく質摂取

たんぱく質は、筋肉量の維持や筋力低下の防止に欠かせない栄養素です。具体的な研究では、適切なたんぱく質摂取が高齢者の筋肉量を維持し、フレイルの進行を遅らせる効果があることが示されています。また、厚生労働省の栄養ガイドラインでは、バランスの取れた食事の一環として、日々のたんぱく質摂取が推奨されています。
ホットヨガスタジオLAVAプチっとメモ!
タンパク質の効果的な摂取方法を分子栄養学アドバイザーの庄司真理子さんがご紹介!
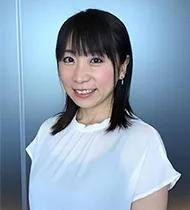
タンパク質の効果的な摂取方法を分子栄養学アドバイザーの庄司真理子さんがご紹介!
タンパク質は、最も大切な栄養素です。まずは一口30回よく噛んで食べましょう。唾液に含まれる消化酵素を沢山出して消化を助ける事が、吸収力を上げる第一段階です。 また、酢の物やレモン水を一緒に摂る事で胃酸を分泌を促します。大根おろしや玉ねぎ、キウイ、パイナップル等を一緒に摂る事で、消化吸収を助ける働きがあります。
毎食、手のひら片手分を目安として摂り、3食以外でもおやつ代わりに補食として摂る事が効果的です。ビタミンB群を一緒に摂る事もオススメです。
ビタミンDとカルシウム

ビタミンDとカルシウムは、骨密度の維持や筋肉機能の改善において不可欠な栄養素です。ビタミンDはカルシウムの効果的な吸収を促進し、骨の健康を保つ役割を果たします。また、カルシウムは骨を強化し、筋肉の収縮や神経伝達を正常に維持するために必要です。これらの栄養素の適切な摂取は、フレイル予防においても重要であり、骨粗しょう症や筋力低下のリスクを低減します。
ホットヨガスタジオLAVAプチっとメモ!
ビタミンDとカルシウムを効率的に摂取する方法を分子栄養学アドバイザーの庄司真理子さんがご紹介!
ビタミンDは、魚介類・きのこ類(干ししいたけ、きくらげなど)・日光浴(1日に10~20分程度)から摂取ができます。
カルシウムは、小魚・干しエビ等の骨も一緒に食べらる食材や、豆腐や納豆などの大豆製品からも摂取する事ができます。
マグネシウムを併せて摂る事で、ビタミンDとカルシウムを効率的に活用する事ができるのでオススメです。
分岐鎖アミノ酸
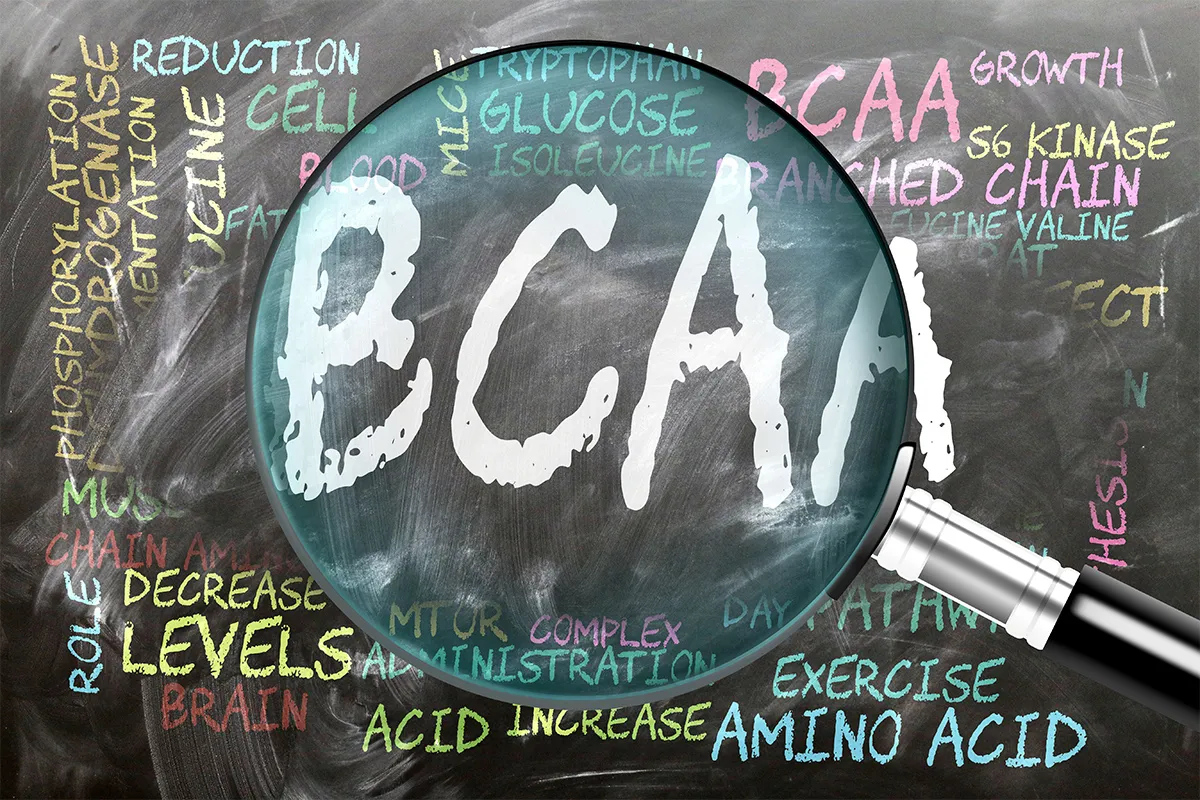
分岐鎖アミノ酸(BCAAs)は、バリン、ロイシン、イソロイシンの3つの必須アミノ酸から構成され、筋肉の修復や成長に欠かせない栄養素として注目されています。これらのアミノ酸は、体内で合成することができないため、食事やサプリメントから摂取する必要があります。
具体的な研究によれば、分岐鎖アミノ酸は、筋肉の合成を促進し、運動後の筋肉痛を軽減する効果があるとされています。また、持続的な運動による筋肉の分解を防ぐ働きも確認されており、高齢者の運動能力維持やフレイル予防において重要な役割を果たします。
ホットヨガスタジオLAVAプチっとメモ!
分岐鎖アミノ酸を効率的に摂取する方法を分子栄養学アドバイザーの庄司真理子さんがご紹介!
アミノ酸は、1度に沢山摂ったとしても貯蔵しておく事ができません。アミノ酸が結合してできるタンパク質は、毎日新しいアミノ酸と入れ替わる事で体を維持しています。 質の良いアミノ酸(タンパク質)を毎日こまめにとる事が健康の秘訣です。
分岐鎖アミノ酸(BCAA)は、鶏肉、牛肉、魚介類、卵、乳製品、ナッツ類などで摂取する事ができます。3食毎1品でも取り入れてみましょう。 バリン・ロイシン・イソロイシンの3成分を配合したサプリメントもあります。運動前後・就寝前・起床時の摂取がオススメです。
企業の取り組み例
1 栄養セミナーの開催
専門家を招いて、栄養素の重要性や効果的な摂取方法について教育します。
2 栄養価の高いメニューの提供
会社のカフェテリアや食堂で、たんぱく質・ビタミンD・カルシウム・分岐鎖アミノ酸を豊富に含むメニューを増やします。
3 栄養補助食品の提供
必要に応じて、サプリメントを従業員に提供します。
4 個別の食事プランの作成支援
栄養士によるカウンセリングを通じて、各従業員に適した栄養摂取プランを提案します。
これらの取り組みを通じて、従業員の健康維持とフレイル予防に寄与することが期待されます。
高齢者の食生活と低栄養のリスク

独居や高齢者世帯の食事傾向
高齢者が独居や高齢者のみの世帯で生活する際には、食事の回数や質に課題が生じやすく、これがフレイルリスクの増加につながります。独居高齢者は、調理の手間や食材の選択に困難を感じることが多く、結果として食事が不規則になったり、栄養バランスが偏ったりする傾向があります。
データによると、独居高齢者の約30%が一日三食を必ずしも摂れておらず、特に夕食を抜くことが多いと報告されています。また、食事の質に関しても、加工食品やインスタント食品に頼る割合が高く、必要なビタミンやミネラル、たんぱく質の摂取が不足しがちです。これにより、筋力低下や免疫力の低下が進行し、フレイルの発症リスクが高まります。
さらに、食事の回数や質が低下することで、精神的な健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。栄養不足は認知機能の低下や抑うつ状態と関連しており、これらが相互に作用してフレイルを悪化させる要因となります。実際に、食事の質が低い高齢者は、栄養バランスが取れている高齢者に比べて、フレイルの発症率が約2倍に上るとの研究結果も存在します。
企業の取り組み例
1 栄養バランスの取れた食事の提供
健康的な社食やお弁当屋出張販売を行う企業もあります。
2 食事に関する教育セミナーの実施
食事のオンラインセミナーも増加しています。
3 食材の購入支援サービスの提供
株式会社LAVA Internationalではオーガニックライフサポート制度として、定価の50%OFFでカラダにいい対象商品が購入可能になる制度があります。
4 オンラインでの食事相談窓口を設ける
さらに、コミュニティベースの食事支援プログラムを企業が支援することで、社会的孤立を防ぎつつ、健康的な食生活をサポートすることが可能です。例えば、定期的な食事会の開催や、料理教室の提供を通じて、従業員同士の交流を促進しながら、食事の質向上を目指す方法があります。これにより、従業員の健康維持だけでなく、職場全体の士気向上にも寄与することが期待されます。
社会的孤立と食生活
社会的孤立は、従業員の食生活の質や摂取量に大きな影響を与えることが多くの研究で明らかになっています。例えば、社会的なつながりの欠如は食事の頻度やバランスの取れた食事の摂取を減少させ、結果として栄養不足や過食につながる可能性があります。
さらに、社会的孤立は心理的なストレスや鬱症状を引き起こし、これが食欲不振や過食を招く要因となることも指摘されています。日本の調査によれば、職場での友人関係が乏しい従業員は、食事の時間や内容において不規則なパターンを示しがちであり、健康維持に必要な栄養素の不足が見られることが確認されています。
企業の取り組み例
1 コミュニティ食事プログラムの導入
定期的な社員食堂やランチイベントを開催し、従業員同士が交流する機会を提供します。
2 チームビルディング活動の推進
スポーツ活動や趣味のグループを形成し、職場外でのつながりを強化します。
3 メンタルヘルスサポートの提供
カウンセリングサービスやサポートグループを設置し、心理的な支援を行います。
4 栄養教育セミナーの実施
栄養バランスの取れた食事の重要性や簡単に実践できる食事法についての教育を行います。
5 フレキシブルな勤務形態の導入
ワークライフバランスを重視し、従業員がストレスを抱えることなく健康的な生活を送れるよう支援します。
これらの施策を通じて、企業は従業員の社会的なつながりを強化し、健康的な食生活の維持をサポートすることが可能となります。結果として、 従業員の健康状態の改善や生産性の向上につながり、企業全体の健全な発展を促進することが期待されます。
食事の工夫と対策

食材選びと調理法
フレイル予防において食材選びと調理方法の工夫は非常に重要です。栄養バランスを保ちながら美味しく食事を摂るためには、新鮮な野菜や果物、良質なタンパク源を選ぶことが基本となります。例えば、筋肉量の維持には高タンパク質食品が不可欠であり、鶏肉や魚、大豆製品などを積極的に取り入れることが推奨されます。また、ビタミンDやカルシウムを豊富に含む食品を選ぶことで、骨密度の維持にも寄与します。
調理方法においては、食材の栄養素を損なわないような、蒸す、茹でる、焼くといった調理法を選ぶことが効果的です。また、オリーブオイルやハーブを活用して風味を加えることで、料理の美味しさを向上させつつ、健康的な食事を楽しむことが可能です。
企業の取り組み例
・従業員に対して健康的な食事の作り方を指導するワークショップを開催
・栄養バランスの取れたレシピ集の提供などのサポートプログラムを導入
口腔機能の低下への対応
口腔機能の低下は、高齢従業員の健康管理において重要な課題です。咀嚼や嚥下の困難は、食事の摂取量や栄養バランスに直接的な影響を与え、フレイルのリスクを高める要因となります。特に、食事の質が低下すると、必要な栄養素の不足に繋がり、筋力低下や免疫機能の低下など、さらなる健康問題を引き起こす可能性があります。
企業の取り組み例
1 適切な食事選択の提供
従業員の口腔機能に配慮した柔らかく、嚥下しやすい食事を提供することで、食事摂取の負担を軽減します。例えば、食材を細かく刻んだり、煮込み料理を取り入れたりなどの工夫が考えられます。
2 栄養補助食品の導入
必要な栄養素を効率的に摂取できるよう、プロテインシェイクやビタミン剤などの栄養補助食品を提供します。これにより、食事だけでは不足しがちな栄養素を補完することが可能です。
3 食事指導と栄養教育
専門の栄養士による食事指導や、口腔機能に配慮した食事の作り方を学ぶセミナーを開催します。従業員が自宅でも実践できる食事の工夫を支援します。
4 口腔ケアのサポート
定期的な歯科検診の実施や、口腔ケア製品の提供を通じて、口腔機能の維持・改善をサポートします。これにより、口腔機能の低下を未然に防ぐことができます。
5 柔軟な勤務体制の導入
食事時間や休憩時間を柔軟に設定し、従業員が無理なく食事を摂取できる環境を整えます。特に、ゆっくりと食事を取る時間を確保することが重要です。
これらの対策を通じて、企業は従業員の口腔機能低下に伴う食事摂取の問題を効果的に支援し、全体的な健康維持とフレイル予防に寄与することができます。従業員一人ひとりの健康状態に応じた柔軟な支援策を導入することで、持続可能な健康管理体制を構築しましょう。
運動によるフレイル予防

筋量減少の防止
筋量減少の防止は、フレイル予防において極めて重要な要素です。筋肉量が減少すると、基礎代謝の低下や身体機能の低下を招き、日常生活や業務遂行に支障をきたす可能性があります。特に高齢従業員においては、筋力の維持・増加が健康維持と直結しており、企業としても積極的な対策が求められます。
まず、運動による筋量維持・増加が不可欠です。日本体育協会のガイドラインでは、週に最低2回の筋力トレーニングを推奨しています。具体的には、ウェイトリフティングやレジスタンスバンドを用いたエクササイズが効果的です。また、有酸素運動と組み合わせることで、全身の筋肉バランスを整え、持久力も向上させることが可能です。
次に、栄養面でのサポートも重要です。特に、たんぱく質の適切な摂取は筋肉の修復と成長に欠かせません。厚生労働省の「高齢者のための食事指針」によると、1日あたり体重1kgあたり1.2gのたんぱく質摂取が推奨されています。さらに、ビタミンDやカルシウムといった栄養素も筋肉機能の維持に寄与します。
企業の取り組み例
1 フィットネスプログラムの導入
社内ジムの設置やフィットネスジムとの提携により、従業員が手軽に筋力トレーニングを行える環境を整備します。
2 栄養セミナーの開催
専門家を招いた栄養指導セミナーを定期的に実施し、適切なたんぱく質摂取やバランスの取れた食事の重要性を啓発します。
3 健康管理アプリの活用
運動や食事の記録を管理できるアプリを導入し、従業員自身が目標を設定しやすい環境を提供します。
歩行能力の維持
歩行能力の維持は、フレイル予防において極めて重要な要素です。歩行速度の低下やバランス能力の低下は、転倒リスクの増加や日常生活の自立度の低下につながりやすく、これらはフレイルの進行を促進します。例えば、歩行速度が1メートル/秒未満になると、日常生活での活動制限や介護の必要性が高まるとの研究結果があります。
歩行能力の向上と維持には、定期的な運動プログラムの導入が効果的です。具体的には、ウォーキングやストレッチ、バランス訓練を組み合わせたプログラムが推奨されます。企業は、従業員が参加しやすいように、職場内でのウォーキングイベントの開催や、フィットネス施設の利用を奨励する取り組みを導入することが有益です。また、歩行速度やバランス能力を定期的に評価することで、早期に問題を発見し、適切な対策を講じることが可能となります。
さらに、バランス能力を維持するためのサポート策として、バランスボードやフィットネスボールを活用したエクササイズの提供や、ヨガやピラティスなどのプログラムを導入することも有効です。これらの取り組みを通じて、従業員の歩行能力を高めるだけでなく、全体的な身体機能の向上にも寄与することが期待されます。企業が積極的に運動プログラムを支援することで、従業員の健康維持と業務パフォーマンスの向上を同時に実現することが可能です。
運動の種類と効果

筋力トレーニング
筋力トレーニングは、フレイル予防において不可欠な要素であり、多様な種類と効果を持つ運動方法を取り入れることで、従業員の健康維持と生産性向上に寄与します。
主な筋力トレーニング
1 ウェイトトレーニング
ダンベルやバーベルを使用して筋肉に負荷をかけることで筋力を強化します。
2 レジスタンストレーニング
バンドや機械を用いて抵抗を加える方法で、特定の筋群を集中的に鍛えることが可能です。
3 自重トレーニング
自身の体重を抵抗として利用するもので、特別な器具を必要とせず、オフィスや自宅でも手軽に実施できます。
筋力トレーニングがフレイル予防にどのように寄与するかについてですが、主に筋肉量の維持と筋力の向上を通じて、身体機能の低下を防ぎます。加齢とともに自然に進行する筋量減少(サルコペニア)を遅らせることができ、これにより歩行速度の維持や転倒リスクの低減につながります。また、筋力が向上することで日常生活動作の自立度が高まり、要介護状態への進行を防ぐ効果も期待できます。
企業の取り組み例
1 フィットネス施設の設置
社内にトレーニングジムを設け、従業員が自由に利用できる環境を整えます。
2 パーソナルトレーナーの導入
専門のトレーナーを配置し、個々のニーズに合わせたトレーニングプランを提供します。
3 オンラインプログラムの提供
在宅勤務者や出張中の従業員向けに、オンラインで参加できる筋力トレーニングセッションを実施します。
4 定期的な健康イベントの開催
筋力トレーニングの重要性を啓発するワークショップやチャレンジイベントを通じて、従業員の参加意欲を高めます。
さらに、モチベーション維持のためのインセンティブを設けることで、継続的なトレーニングの実施を促進することが可能です。例えば、達成目標に応じた報奨制度や、トレーニング達成者の表彰などが効果的です。
総じて、筋力トレーニングはフレイル予防において非常に重要な役割を果たします。企業が積極的に従業員に対して適切なトレーニングプログラムを提供し、健康的なライフスタイルを促進することで、従業員の健康維持と企業全体の生産性向上を実現することができます。
有酸素運動
有酸素運動は、心肺機能の向上や全身の健康維持に欠かせない運動です。定期的に有酸素運動を行うことで、血液循環の改善や酸素供給能力の向上が促され、持久力の向上や代謝の活性化につながります。また、ストレスの軽減やメンタルヘルスの向上にも効果的であり、従業員の生産性や職場全体の活力向上に寄与します。
主な有酸素運動
・ウォーキング
・ジョギング
・サイクリング
・水泳 など
有酸素運動の推奨頻度は、週に150分以上の中程度の強度、または75分以上の高強度の運動を目安としています。これを1日に分けて行うことで、継続しやすくなります。例えば、毎日30分のウォーキングを行うことで、目標の時間を達成することが可能です。
企業の取り組み例
1 フィットネスチャレンジの実施
従業員がチームを組んで目標歩数を競うなど、楽しみながら運動を促進します。
2 社内ジムやランニングクラブの設置
職場に運動スペースを設け、自由に利用できる環境を提供します。
3 定期的な運動セミナーやワークショップの開催
専門家を招いて、有酸素運動の重要性や正しい実施方法を教育します。
4 休憩時間を利用したストレッチや軽運動の推奨
短時間で実践できる運動を促し、日常生活に運動を取り入れる習慣を作ります。
これらのプログラムを通じて、従業員の健康意識の向上と運動習慣の定着を図り、結果として企業全体の健康維持と生産性向上につなげることが可能です。
バランス運動
バランス運動は、転倒リスクの低減や日常生活の自立度維持に非常に重要な役割を果たします。特に高齢者においては、バランス能力の低下がフレイルの進行や生活機能の低下に直接的に影響を与えるため、早期からのバランス運動の導入が推奨されます。
主なバランス運動
1 片足立ち
片足で立ち、バランスを保つ練習を繰り返すことで、下肢の筋力とバランス感覚を強化します。
2 太極拳
ゆっくりとした動きで全身を使う運動で、バランスと柔軟性を同時に向上させます。
3 バランスボードの使用
バランスボードに乗ることで、不安定な状態でのバランス維持を訓練します。
4 ヨガ
バランスを保つポーズを左右均等に行うことで、偏りのない体幹をつくります。
企業の取り組み例
1 定期的なバランス運動セッションの開催
オフィス内や近隣のフィットネスセンターで、専門インストラクターによるバランス運動クラスを実施します。
2 オンラインプログラムの提供
在宅勤務者や忙しい従業員向けに、動画を利用したバランス運動プログラムを提供します。
3 バランス運動器具の導入
バランスボードや安定ボールなどの運動器具をオフィスに設置し、従業員が自由に利用できる環境を整備します。
これらの取り組みにより、従業員のバランス能力が向上し、健康維持や業務効率の向上に繋がることが期待されます。バランス運動は手軽に始められる上、継続的に取り組むことで大きな効果を実感できます。企業としても、積極的にバランス運動の推進を図ることで、従業員の健康管理に貢献することが可能です。
フレイル予防のための健康管理部門の取り組み

定期的な健康診断の実施
定期的な健康診断は、従業員のフレイル予防において不可欠な役割を果たします。健康診断を通じて、筋力低下や体重減少、歩行速度の遅さなど、フレイルの早期兆候を迅速に把握することが可能です。これにより、従業員一人ひとりに適した予防策を講じることができ、フレイルの進行を未然に防ぐことができます。
また、健康診断による早期発見と介入は、フレイル予防において非常に重要です。例えば、ある企業では定期的な健康診断を実施することで、従業員の筋力低下を早期に検出し、適切な運動プログラムや栄養指導を提供することで、フレイルの進行を効果的に抑制しています。この取り組みにより、従業員の健康維持だけでなく、欠勤率の低下や生産性の向上にも寄与しています。
企業の健康管理部門が効果的な健康診断プログラムを設計・運用するためには、以下の点が重要です。まず、フレイルに関連する指標を健康診断の項目に積極的に取り入れること。次に、診断結果に基づいた個別の健康支援プランを提供し、従業員が継続的に健康管理を行えるようサポート体制を整えることです。さらに、従業員が健康診断を受けやすい環境を整備し、定期的なフォローアップを実施することで、早期発見と迅速な介入を実現します。
最後に、健康診断のデータを活用して企業全体の健康傾向を分析し、職場環境の改善や健康教育の強化につなげることも重要です。これにより、従業員全体の健康意識が向上し、持続可能なフレイル予防対策を展開する基盤を築くことができます。
予防・早期発見・治療の促進
フレイルの進行を防ぐためには、予防、早期発見、そして効果的な治療介入が不可欠です。企業の健康管理部門は、これらの取り組みを積極的に推進することで、従業員の健康維持と生産性の向上に寄与できます。
予防策
定期的な健康診断の実施や、バランスの取れた栄養管理、適度な運動の推奨が挙げられます。これにより、筋力低下や栄養不足など、フレイルのリスク要因を未然に防ぐことが可能です。
早期発見
従業員の健康状態を継続的にモニタリングし、フレイルの兆候を早期に察知する体制を整えることが重要です。具体的には、Friedの5項目基準やFrailty Indexを活用した評価ツールの導入が有効です。
治療介入
見つかったフレイル症状に対して、適切な運動プログラムや栄養補助、必要に応じて専門医への紹介を行うことが求められます。企業は、これらの介入をサポートするための健康プログラムを設計・提供することが重要です。
企業の取り組み例
・定期的な健康セミナーやワークショップの開催
・従業員向けのフィットネスプログラムや栄養相談サービスの提供
・健康管理システムの導入によるデータの一元管理と分析
・フレイル予防専用の社内チームや担当者の配置
これらの施策を通じて、企業は従業員の健康維持を支援し、フレイルの進行を効果的に防止することができます。
従業員への啓発と支援

運動や食事の情報提供
フレイル予防のために、運動や食事に関する情報提供は欠かせません。従業員が健康的な生活習慣を維持するためには、正確で分かりやすい情報を適切な形式で提供することが重要です。
運動プログラム
ガイドラインや具体的なエクササイズ方法を紹介することで、従業員が日常生活に取り入れやすい運動習慣を形成できます。これには、ストレッチや筋力トレーニング、有酸素運動など多様な運動メニューを含めることが有効です。
食事プログラム
栄養バランスの取れた食事プランや健康的なレシピを提供することで、従業員が食生活を見直しやすくなります。特に、たんぱく質やビタミンD、カルシウムなどフレイル予防に必要な栄養素の摂取方法について詳しく説明することが重要です。
情報提供の形式としては、社内ニュースレターやオンラインポータルを活用することが効果的です。これにより、いつでもアクセス可能な情報源を提供することができます。また、ウェビナーやワークショップを定期的に開催することで、従業員同士の交流を促しながら知識を深める機会を作ることも推奨されます。
さらに、モバイルアプリやデジタルツールを活用することで、従業員が手軽に情報にアクセスし、自己管理をサポートすることが可能です。例えば、食事の記録や運動の進捗を追跡できるアプリを導入することで、継続的な健康管理を支援できます。
最後に、定期的なフィードバックやアンケートを実施し、従業員のニーズや興味に応じた情報提供を行うことで、より効果的な健康支援が実現できます。これにより、従業員の積極的な参加と健康意識の向上を促進することができます。
健康増進プログラムの提供
フレイル予防を目的とした包括的な健康増進プログラムの設計は、運動、食事、社会活動など多岐にわたる要素を統合的に取り入れることが重要です。まず、従業員の健康状態やニーズを把握するために、定期的な健康チェックやアンケート調査を実施し、個々のフレイルリスクを評価します。これに基づき、運動プログラムでは筋力トレーニングや有酸素運動、バランス運動を組み合わせ、筋肉量の維持・増加や歩行能力の向上を図ります。
食事面では、栄養指導セッションを開催し、たんぱく質やビタミンD、カルシウムなどの重要な栄養素の摂取を促進する食事プランを提供します。また、従業員が楽しみながら健康的な食事を続けられるよう、ヘルシーなレシピの共有や社内での料理教室の開催など、実践的なサポートを行います。
さらに、社会活動の促進もフレイル予防には欠かせません。社内の健康イベントやチームビルディング活動を通じて、従業員同士の交流を深めることで、社会的なつながりを強化し、孤立を防ぎます。実際に、某大手企業では、定期的にヨガやウォーキングクラブを導入し、従業員の参加率と満足度が大幅に向上したとの報告があります。これらの取り組みにより、企業は従業員の健康維持をサポートし、生産性の向上や医療コストの削減にも寄与することができます。
事例
株式会社トライネットでは健康経営の一環として、ホットヨガスタジオLAVAの健康増進プログラムを取り入れ、担当者様から「ヨガを通して普段話さない別部署の社員とも交流が取れ、コミュニケーションツールとしても優秀だったと思います。」と他部署とのつながりも強化することができました。
参考:LAVA法人向けサービス導入実績株式会社トライネット株式会社様まとめと今後の展望

本記事では、企業におけるフレイル予防の重要性と、食事・運動を通じた具体的な対策について解説してきました。
フレイル予防は、従業員個人の健康寿命延伸はもちろんのこと、企業の生産性向上、医療費抑制、そして貴重な人材の確保という観点からも、極めて重要な経営課題です。従業員の活力は、企業の活力そのものであり、企業の健康管理部門には、このフレイル予防を推進し、従業員一人ひとりが健康でいきいきと働ける職場環境を整備する中心的な役割が期待されます。
今後の展望としては、一過性の取り組みに終わらせず、従業員のニーズやライフステージの変化に合わせた、持続可能で柔軟なフレイル予防プログラムを展開していくことが成功の鍵となります。定期的な効果測定と改善を重ね、企業と従業員双方にとって価値のある健康経営を目指しましょう。