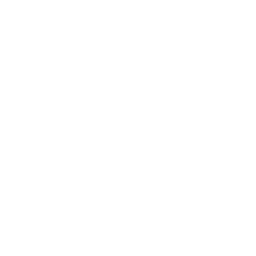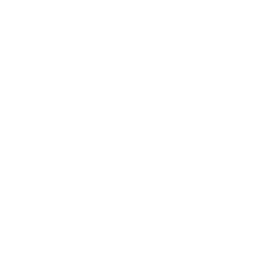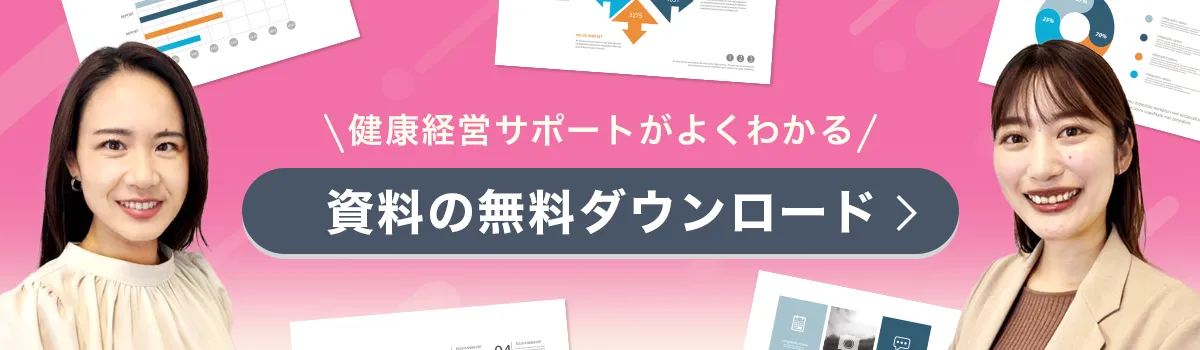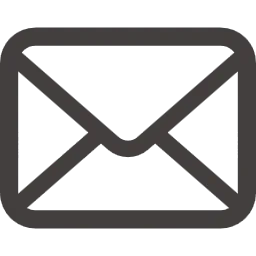多様な人材で労働力不足を解消!高齢者・女性活用の成功事例4選

日本は少子高齢化により急速に人口減少社会へと移行し、労働力不足が深刻化しています。特に建設業、運輸業、医療・福祉業界での人手不足が顕著です。労働力の減少は経済成長や社会保障制度にも影響を及ぼし、企業は多様な人材の活用やリスキリング、DX推進などの戦略を通じて持続可能な成長を目指す必要があります。
このコラムでは、これらの具体的な成功事例を紹介します。労働力不足解消のためにご参考ください。
なぜ労働人口減少が深刻なのか?

進む少子高齢化と生産年齢人口の縮小
日本では生産年齢人口の減少が急速に進行しており、これに伴い労働力人口の縮小が深刻な課題となっています。総務省統計局のデータによると、2023年時点で生産年齢人口は前年に比べ約1.2%減少しており、2035年にはさらに大幅な減少が予測されています。この傾向は、特に建設業、運輸業、医療・福祉業界などで顕著に現れています。
参考:総務省統計局 参考:国土交通省例えば、建設業では熟練工の高齢化が進み、新規参入者が不足しているため、大型プロジェクトの遂行に支障をきたすケースが増えています。同様に、運輸業ではドライバー不足が深刻化しており、物流の遅延やコスト増加が頻発しています。医療・福祉業界では、介護スタッフの不足が高齢化社会に対応する上で大きな障害となっており、サービスの質低下や労働環境の悪化が懸念されています。
社会・経済に与える影響
少子高齢化が進行する中で、日本は急速に人口減少社会へと移行しています。この現象は、出生率の低下と高齢者の割合増加によって引き起こされており、企業や社会全体に多大な影響をもたらしています。
労働力不足は、その最たる影響の一つです。若年労働人口の減少により、特に建設業、運輸業、医療・福祉業界などで深刻な人手不足が発生しています。これにより、企業は採用競争の激化や業務効率の低下に直面し、生産性の維持が困難となっています。
また、経済成長への影響も無視できません。労働力の減少は、消費の縮小やイノベーションの停滞を招き、長期的な経済成長を阻害する要因となります。企業は市場の縮小に対応するため、新たなビジネスモデルの開発や海外市場への進出を余儀なくされることもあります。
社会保障制度への負担増加も深刻な問題です。高齢者人口の増加に伴い、年金や医療費などの社会保障費が急増しています。これにより、現役世代の負担が増加し、働き方改革や生産性向上が一層求められる状況となっています。
企業が直面する課題
人手不足と業務効率の低下
限られた人材で業務をこなさなければならないため、従業員一人当たりの負担が増加し、結果として業務効率が低下する傾向があります。また、業務負担の増加は従業員のストレスや疲労を招き、離職率の上昇につながることも懸念されています。
長時間労働と健康リスク
長時間労働が常態化すると、従業員の健康問題が深刻化するリスクが高まります。例えば、過労により心身の不調を訴える従業員が増加し、結果として生産性の低下や離職率の上昇を招く可能性があります。さらに、慢性的なストレスは職場全体の雰囲気にも悪影響を及ぼし、チームワークの崩壊や企業の評判低下にも繋がりかねません。
人材流出と採用難の悪循環
離職率の上昇は、人材不足をさらに深刻化させる負のスパイラルを引き起こします。高い離職率は、企業における経験豊富な人材の喪失だけでなく、採用コストの増加や新人教育への負担増大を招きます。これにより、企業は更なる人材確保が困難となり、結果として生産性の低下や業務の効率化への課題が浮き彫りになります。
企業が取り組むべき3つの対策

多様な人材の活用
高齢者:経験とノウハウの活用
高齢者の豊富な経験とノウハウを活かすことで、企業の業務改善に大きく貢献できます。高齢者が長年培ってきた専門知識やスキルは、組織内での知識の継承や問題解決能力の向上に役立ちます。具体的には、以下のような方法で高齢者の経験を組織に取り入れることが可能です。
まず、高齢者をメンターとして若手社員と連携させることで、実務経験に基づく指導を行います。これにより、若手社員は実践的なスキルを効率的に習得し、業務の質を向上させることができます。また、定期的なワークショップや研修を開催し、高齢者が持つ専門知識を全社員に共有する場を設けることも効果的です。
さらに、プロジェクトベースでの協働を推進することで、異なる世代間の相互理解とチームワークを強化します。例えば、医療業界では経験豊富な看護師が若手看護師と共同で患者ケアの改善プロジェクトを進めることで、現場の効率化やサービス品質の向上が実現されています。
女性:働きやすい環境と支援制度
女性の労働参加率を向上させ、より働きやすい環境を作るために、企業は育児支援制度の充実や柔軟な勤務時間の導入、職場内でのジェンダー平等の推進など、さまざまな取り組みが必要とされます。
・育児支援制度の充実
産休・育休の取得を容易にするほか、保育サービスの提供や子育て休暇の拡充などが挙げられます。これにより、子育てと仕事の両立がしやすくなり、女性の継続的な就業を支援します。
・柔軟な勤務時間の導入
テレワークやフレックスタイム制度の採用が進められています。これにより、社員は生活スタイルに合わせた働き方が可能となり、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなります。
・職場内でのジェンダー平等の推進
性別に関係なく昇進の機会を提供することや、ハラスメント防止の研修を行うことなどが含まれます。これにより、女性が安心して活躍できる職場環境が整います。
これらの施策を実施することで、企業は女性の労働参加率を向上させるだけでなく、企業全体の生産性やイノベーションの促進にもつながります。実際に、多くの企業がこれらの取り組みにより、女性社員の定着率や満足度を向上させる成果を上げています。
柔軟な働き方と健康経営の推進
テレワークや時短勤務などの導入
柔軟な働き方の導入も重要なポイントです。テレワークやフレックスタイム制など、従業員のライフスタイルに合わせた働き方を提供することで、従業員の満足度を高め、離職率の低減に繋げることができます。
・パートタイム勤務:労働時間を短縮することで、体力的な負担を軽減し、長期間にわたり働き続けることが可能となります。
・フレックスタイム制度:始業・終業時間を柔軟に設定できることで、個々のライフスタイルや健康状態に合わせた働き方が実現できます。
・リモートワーク:在宅勤務を導入することで、通勤の負担を減らし、自宅での作業環境を整えることで生産性を維持・向上させることができます。
従業員の定着率と満足度向上
無理なく働ける職場環境の整備や賃金格差の解消およびキャリアアップ支援等、従業員の満足度を向上させることも企業にとっては欠かせない対策です。
従業員の満足度向上の為には前途したように、育児支援制度の充実や柔軟な勤務時間の導入は、共働き世帯が増えている昨今には必要不可欠となっています。
また健康経営を実践することで、企業は単に従業員の健康を守るだけでなく、持続可能な労働環境を構築することができます。具体的な方法として、健康診断の充実やメンタルヘルス対策の強化、福利厚生の充実などが考えられます。これにより、従業員は安心して働ける環境が整い、企業としての信頼性や魅力も向上します。
柔軟な働き方を支援する取り組みは、現代の多様化する労働環境において欠かせません。おうちde LAVAを活用することで、健康経営と働き方改革を同時に推進し、持続可能な企業運営を実現することができます。ぜひ、おうちde LAVAを導入して、従業員の健康と企業の発展を両立させましょう。
DXとリスキリングによる生産性向上
AI・デジタル化の実装手順
デジタル技術を活用することで、企業は業務プロセスを効率化し、労働力不足に対応することが可能です。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やクラウドコンピューティング、人工知能(AI)などの先進技術は、日常業務の自動化やデータ管理の最適化を実現し、従業員の負担を軽減します。
業務プロセスの見直しを進めるための手順は以下の通りです。
・現状の業務プロセスを分析:各部署の業務内容とフローを詳細に把握します。
・改善が必要なポイントを特定:効率が悪い部分や自動化可能な業務を洗い出します。
・適切なデジタル技術を選定:RPAやクラウドサービス、AIツールなど、目的に合った技術を選びます。
・導入とトレーニング:選定した技術を導入し、従業員へのトレーニングを実施します。
・効果測定と継続的改善:導入後の効果を評価し、必要に応じてプロセスを調整します。
例えば、某運輸業界の企業ではRPAを導入することで、請求書処理の時間を従来の半分に短縮し、従業員はより価値の高い業務に集中できるようになりました。このような成功事例は、デジタル技術が実際に業務改善に寄与することを示す良い例です。
キャリア支援とスキルアップの場づくり
いま、多くの企業が直面しているのは「人材の定着」と「成長機会の提供」という課題です。従業員一人ひとりが自分のキャリアに希望を持ち、学び続けられる環境を整えることは、モチベーションの向上だけでなく、企業全体の競争力を高めるうえでも欠かせません。
まず大切なのは、明確なキャリアパスの提示です。将来のビジョンが見えることで、従業員は自らの成長に前向きになり、日々の業務にも意欲的に取り組むようになります。
また、定期的な研修やスキルアップの機会も重要です。専門性を高める研修や、次世代リーダーを育てる講座などを通じて、従業員は新たな知識を吸収し、役割の幅を広げていくことができます。さらに、メンター制度を導入すれば、経験豊富な社員が若手を支え、組織全体で知見を共有する文化が育まれます。
最近では、オンライン学習プラットフォームの活用も進んでいます。時間や場所にとらわれず、自分のペースで学べる環境は、仕事と学びの両立を可能にし、働きながら成長できる柔軟な働き方を支えます。
そして忘れてはならないのが、継続的なフィードバックと評価制度です。定期的な面談やパフォーマンスレビューを通じて、努力や成果を正しく認め、次のステップに向けた具体的なアドバイスを行うことで、従業員の成長意欲をさらに引き出すことができます。
こうした取り組みを積み重ねることで、従業員が「この会社で成長できる」と実感できる環境が整い、結果として企業の持続的な成長にもつながっていきます。
事例で学ぶ!人材確保の成功パターン

運輸業:高齢者ドライバーの再雇用
運輸業界では、高齢者の豊富な経験と確かなスキルが業務改善や効率化に大きく貢献しています。例えば、ある運送会社では、長年にわたり培った運転技術や物流管理の知識を持つ高齢社員が、若手社員の教育や現場の改善プロジェクトに積極的に関与しています。
その会社では高齢者専用のトレーニングプログラムを導入し、彼らの経験を体系化して新入社員に伝える仕組みを構築しました。その結果、若手社員のスキル向上と業務効率の改善が実現し、全体の生産性が顕著に向上しました。さらに、高齢者の知見を活かした業務プロセスの見直しにより、作業の標準化や無駄の排除が進み、他の業界でも応用可能なベストプラクティスとして注目されています。
製造業:若手育成とDX融合(日立など)
日立製作所では、リスキリングを通じた人材育成に取り組み、業務効率の向上と従業員のエンゲージメント強化を図っています。
従業員一人ひとりのスキルギャップを可視化し、製造ラインの自動化やデジタルツールの導入に対応するために必要なスキルを明確化し、その上で、以下のような施策を展開しています。
・オンライントレーニングの提供:最新の製造技術やデジタルツールに関するオンラインコースを整備し、従業員が自分のペースで学べる環境を構築。
・実践的なワークショップの開催:現場で活用できるスキルを身につけるためのハンズオン形式の研修を実施。
・メンター制度の導入:経験豊富な社員が学習をサポートし、スキルの定着と実践への応用を支援。
・定期的な評価とフィードバック:スキル習得の進捗を確認し、個々の成長に合わせたアドバイスを提供。
これらの取り組みにより、従業員のスキル向上だけでなく、自律的なキャリア形成を後押しする風土が醸成されつつあります。結果として、従業員の満足度や定着率の向上にもつながっており、企業全体の生産性向上にも寄与しています。
たとえば、製造ラインの自動化により作業時間の短縮や品質管理の精度向上といった効果も報告されており、リスキリングが企業の競争力強化に直結する施策であることが示されています。
他企業がこの成功事例から学べるポイントとしては、従業員一人ひとりのスキルニーズを的確に把握し、個別に対応することの重要性が挙げられます。また、継続的なサポート体制を整えることで、リスキリングの効果を最大化することが可能です。これらの具体的な施策を参考に、自社に合ったリスキリングプログラムの導入を検討することをおすすめします。
情報サービス業:AI導入と業務効率化(KDDIなど)
KDDI株式会社では2022年にDX推進本部を新設し、企業の業務効率化や新規事業創出を支援する体制を整えました。特に注目すべきは、IoTや5Gといった先端技術を活用し、現場の負担を軽減しながら、従業員が活躍できる環境を整えている点です。
たとえば、地方自治体と連携した農業・漁業分野での5G活用では、誰でも扱いやすい遠隔監視システムを導入しました。これにより、経験豊富な従業員の知見を活かした持続可能な働き方が実現しています。
また、ガス検針業務の自動化では、体力を要する業務をデジタル化することで、より安全で柔軟な働き方への転換を支援しています。
女性活用:育児支援とキャリア支援の好循環(東ソー・エイアイエイ)
東ソー・エイアイエイ株式会社では、子育て支援制度の充実を図りました。具体的には、育児休業の最初の5日間を有給化や育児休暇・介護休暇を1分単位で取得可能な制度の導入、相談窓口と掲示板を設置し、仕事と家庭の両立支援の内容を周知など、育児している従業員の働き方をサポートしています。
これらの取り組みを5年間行ったことで、女性従業員の育児休業取得率100%はもちろん、男性従業員の育児休業取得率が2021年から100%を達成しました。仕事と育児の両立支援により、全社的に効率的な働き方が浸透し、残業時間は月平均3時間に減少しました。2023年にユースエール認定、2024年にくるみん認定を取得できました。これらの認定を活用し、採用応募者が増加し、直近3年間で14名の若手従業員が入社、定着率は86%に向上しました。育児休業を取得する従業員の仕事をカバーする体制も整備されました。
※ イー・クオーレ調べ:2020年10月(首都圏・京阪神在住の20~59歳の女性で、調査対象施設(ホットヨガ・フィットネス)を現在利用している方(施設の抽出は、売上高、店舗数、会員数において上位の会社をピックアップ)600名を対象にインターネット調査。)
まとめ:人口減少社会を乗り越える人材戦略とは

持続可能な社会を実現するためには、多様な人材を確保し、その能力を最大限に活用することが不可欠です。これには、働き方改革、リスキリング、多様な背景を持つ人々の積極的な活用が含まれます。
・働き方改革では、柔軟な勤務時間やリモートワークの導入が進んでいます。これにより、従業員のワークライフバランスが向上し、企業の業務効率も改善されます
・リスキリングは、従業員が新たなスキルを習得するための教育プログラムです。これにより、労働力の質が向上し、企業の競争力が強化されます。
・多様な人材の活用も重要です。高齢者や女性など、異なるバックグラウンドを持つ人々を積極的に雇用することで、組織内に多様な視点やアイデアが生まれ、イノベーションが促進されます。
これらの取り組みは、持続可能な社会の実現に直結しています。企業がこれらの施策を継続的に推進することで、長期的な人材戦略を構築し、社会の発展に貢献することが可能となります。