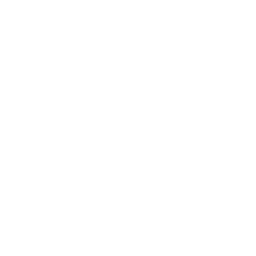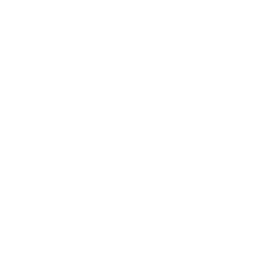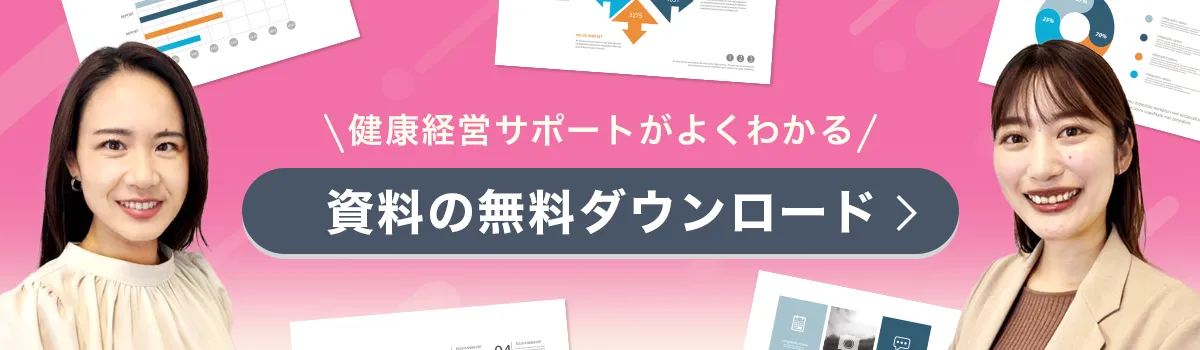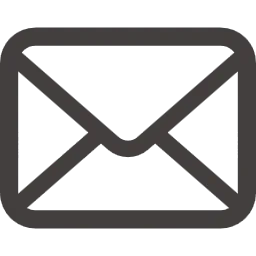管理職のメンタルヘルスケア|効果的なストレス対策とは【事例あり】

部下のマネジメントに加え、プレッシャーや責任も大きい管理職。 あなたの職場では、メンタルヘルス対策は万全ですか?この記事では、管理職特有のメンタルヘルスの課題と、具体的な対策事例、そして施策を成功させるためのポイントを紹介します。 企業の未来を担う管理職を守るために、いますぐできることを始めましょう。
管理職が抱えるストレスの原因とは?

管理職が抱えるストレスの原因は多岐にわたります。以下では主な原因について具体的に説明します。
仕事のプレッシャーや目標達成の要求:常に高い成果を求められる環境下で、期限に追われることや目標達成のプレッシャーがストレスの大きな要因となります。
部下の管理やチーム運営に伴う課題:部下の能力やモチベーションを適切に管理し、チームとしての目標を達成するためのリーダーシップが求められることがストレスを引き起こします。
組織内での役割期待と実際の業務とのギャップ:上司や経営陣から期待される役割と、実際に担当する業務との間にギャップがある場合、役割の不明確さや責任感の重さからストレスが生じます。
中間管理職の特有のストレス
中間管理職に特有のストレスは、組織内で上司と部下の間に立つ役割を担うことで生じます。上からの指示を部下に伝達し、部下の要求や問題を上層部に報告するという二重の責任を負うことで、業務量の増加や調整業務による負担が増し、時間的プレッシャーや人間関係の複雑化など、特有の課題に直面します。
これらのストレス要因は、中間管理職自身のメンタルヘルスに悪影響を及ぼすだけでなく、組織全体の生産性低下や離職率の増加といった問題を引き起こす可能性があります。したがって、中間管理職に対する適切なストレス対策は、個々の健康維持のみならず、組織全体の健全な運営にも不可欠です。
持続的なストレスは、管理職の離職率を高めるだけでなく、企業の評判にも悪影響を及ぼします。また、メンタルヘルス不調による医療費や休職費用の増加など、長期的な経済的リスクも顕在化します。これらのリスクに対処しないことで、企業の持続可能な成長が妨げられる恐れがあります。
LAVAのプチっとメモ!
実際に管理職として活躍中の株式会社LAVA International法人営業部マネージャー 松田えりこさんにお話を伺いました。

管理職として働く中で、どのようなストレスを感じることがありますか?
松田さん「グループの管理職として、正しい情報を得ながらオペレーションをするという緊張感もありますし、上司、部下、他部署、取引先など、立場や役割、価値観が異なるさまざまな方と関わるため、相互理解が図れないときにはストレスを感じることもあります。また、自身の実務を行いながら、会議や面談など時間がとられることが多々増えますし、指示もしなければならないこともあり、スピード感も求められる。トラブルがあれば、それにも対処しなければなりませんので業務量は多いです。自分が管理職としてのミッションをどこまで果たせるのか、と日々葛藤もしています。
そのようなストレスによって、ご自身の業務上への影響を感じたことはありますか?」
松田さん「冷静に振り返ると影響が出ていることもあります。心身の疲れがたまっているときは、ディスカッションする場でアイディアが出なかったり、睡眠が足りていないときは、判断ミスが増えがちなど、集中力、生産性が低下しているように思います。」
ストレス対処法として実践されていることはありますか?
また社内でのこのようなサポートがあると嬉しい、など期待することはありますか?
松田さん「相談できる人をつくっておくこと、簡単にでもカラダを動かすこと、目を閉じ深い呼吸をすること、を意識して行っています。 部下に対してもですが、それと同様に管理職自身が自分でメンタルヘルスケアできることも重要ですが、そのためには、まずは、自分のストレスを認識する必要がありますので、自身への感度を高めていかないといけないと感じています。
とはいえ、管理職は業務量が多いです。会社は、知識面の管理職研修だけでなく、管理職者が不調に陥っていないか自覚する時間を設ける、 メンタルヘルスケアについて教育することが今後の持続可能な企業活動には必要不可欠と思います。」
管理職が抱えるストレスを個人の問題とせず、企業としてどのように対策を取るべきか考える必要があります。以下より4つの具体的取り組み事例を紹介します。
管理職のメンタルヘルスケアに効果的な取り組み事例
取組事例➀管理職向けのストレス管理研修

管理職向けのストレス管理研修は、企業が持続可能な成長を遂げるために欠かせない施策です。現代のビジネス環境では、管理職が抱えるストレスが組織全体のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、効果的なストレス管理が求められています。
研修の目的と必要性を明確にし、管理職が直面する様々なストレス要因に対処するためのスキルを提供します。また、研修を通じて達成すべき目標や期待される成果についても詳しく解説します。
管理職研修の内容と目的
管理職研修では、ストレスマネジメントやリーダーシップなど、管理職に必要な主要なテーマやスキルを取り扱います。これらのテーマは、管理職が直面するさまざまな課題に対応し、効果的にチームを導くための基盤を築くことを目的としています。
各テーマの具体的な目的としては、ストレスマネジメントでは管理職自身のストレスを適切に管理し、健全な職場環境を維持する方法を学びます。リーダーシップでは、チームを効果的にリードし、モチベーションを高めるスキルを習得します。これにより、管理職は自身の業務負荷を軽減しながら、部下のパフォーマンス向上にも貢献できます。
これらの研修を通じて、組織全体にポジティブな影響が広がります。管理職が効果的なストレス管理とリーダーシップスキルを身につけることで、チーム全体の生産性が向上し、健全な職場文化の醸成につながります。
研修を通じたスキルアップ

管理職向けの研修プログラムは、ストレスマネジメントやリーダーシップスキルの向上に重点を置いています。具体的な研修内容としては、自己認識の強化、効果的なコミュニケーション技術、問題解決能力の開発などが含まれます。これらのスキルは、管理職が日常業務を効率的に遂行し、チームを効果的に導くために不可欠です。
スキルアップは、業務の生産性向上やチームの士気を高める具体的な効果をもたらします。例えば、効果的なコミュニケーション技術を習得することで、部下との意思疎通がスムーズになり、業務の効率化が図られます。また、問題解決能力の向上は、突発的な課題に迅速に対応する力を養い、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。
さらに、継続的な学習と成長は、管理職自身のキャリア発展にとっても重要です。定期的な研修を通じて最新の知識やスキルを習得し続けることで、管理職は変化するビジネス環境に柔軟に対応できるようになります。これにより、個人としての成長はもちろん、組織全体のメンタルヘルス向上にも繋がります。
新任管理職の育成と支援
新任管理職は、多くの特有の課題に直面します。例えば、限られた経験の中でチームを効果的にリードすることや、部下との信頼関係を築くことなどがあります。これらの課題に対処するためには、適切な育成と支援が不可欠です。
効果的な育成プログラムとしては、リーダーシップ研修やコミュニケーションスキルの向上を目的とした研修が挙げられます。また、メンター制度の導入や定期的なフィードバックセッションを通じて、新任管理職をサポートする体制の構築が重要です。
新任管理職への早期サポートは、組織全体にポジティブな影響を与えます。適切なサポートを受けた管理職は、部下のモチベーションを高め、生産性の向上につながるため、組織の健全な発展に寄与します。
取組事例②産業医による支援とストレスチェック

産業医の役割と支援内容
産業医は、従業員のメンタルヘルスを支えるために欠かせない存在です。彼らは企業内でカウンセリングや健康相談など、具体的なサポートを提供し、従業員が抱えるストレスや悩みを解消する手助けを行います。
さらに、産業医は組織内で健康管理の専門家として重要な役割を果たしています。彼らは従業員の健康状態を定期的にチェックし、職場環境の改善や労働条件の見直しなど、組織全体の健康維持に貢献します。
産業医との連携は、メンタルヘルス向上に大きな効果をもたらします。産業医の専門知識と組織のサポート体制が融合することで、より効果的なメンタルヘルスケアが実現し、職場全体の生産性や従業員の満足度向上につながります。
ストレスチェックの重要性
ストレスチェックは、メンタルヘルスケアにおいて欠かせないツールです。これにより、従業員のストレス状況を定期的に把握し、早期に問題を発見することが可能となります。組織全体の健康状態をモニタリングすることで、効果的な対策を立案し、実施する基盤を提供します。
さらに、ストレスチェックの実施は法的な義務として位置付けられており、企業は労働安全衛生法に基づいて適切な対応が求められます。これにより、従業員の健康管理を徹底し、職場環境の改善につなげることができます。
取組事例③管理職同士の支援と部下とのコミュニケーション

管理職同士の相互支援の重要性
管理職同士の相互支援は、情報共有や感情的サポートを通じて組織全体のメンタルヘルスを向上させる重要な要素です。 相互支援によって、管理職は業務上の課題やストレスを共有し、効果的な解決策を見つけることができます。また、感情的なサポートを受けることで、自己のメンタルヘルスを維持しやすくなります。
効果的な相互支援を実現するためには、以下の方法が有効です。
・定期的なミーティングや情報交換の場を設けること
・オープンなコミュニケーションを促進し、意見交換を活発にすること
・共通の課題に対する協力体制を構築すること
これらの取り組みを通じて、管理職同士の連携が強まり、組織全体のメンタルヘルスが向上します。結果として、職場の雰囲気や生産性の向上にもつながるのです。
部下とのコミュニケーションのスキル
管理職にとって、部下との効果的なコミュニケーションスキルは不可欠です。傾聴や適切なフィードバックなど、基本的なコミュニケーション技術を身につけることで、部下との信頼関係を築く基盤となります。
また、部下との信頼関係構築は、日々の業務を円滑に進めるために重要です。具体的な方法としては、定期的な1on1ミーティングの実施や、部下の意見を積極的に取り入れる姿勢が挙げられます。
さらに、コミュニケーションがストレス管理に与える影響についても理解する必要があります。オープンな対話を促進することで、部下が抱えるストレスを早期に把握し、効果的なサポートを提供することが可能になります。
取組事例④企業による管理職のメンタルヘルスケア対策

メンタルヘルスケアへの取り組み
企業内でのメンタルヘルスケアの重要性は、従業員の生産性や職場環境の健全性を維持する上で欠かせません。特に管理職のメンタルヘルスは、組織全体のパフォーマンスに大きく影響を与えるため、適切なケアが求められます。
具体的な取り組み事例としては、相談窓口の設置やメンタルヘルス教育の実施が挙げられます。これにより、管理職が抱えるストレスや悩みを早期に発見し、専門的なサポートを提供することが可能となります。
最新トレンド|管理職のメンタルヘルス対策として注目される「セルフケア支援」

これまで紹介してきた取り組みに加えて、近年注目されているのが“セルフケア”を支援する取り組みです。マインドフルネスなど、日常的に取り組めるストレスケアは特に管理職において有効とされ、外部サービスの導入も進んでいます。
セルフケアの重要性とマインドフルネスの活用
マインドフルネスとは、現在の瞬間に意識を集中させる心の状態で、特にストレスの解消に効果的です。瞑想や呼吸法を通じて実践され、今ここにある自分の感覚や感情に気づき、それを評価せずに受け入れることが基本です。これにより、心の安定やリラクゼーションが促進され、ストレス管理がしやすくなります。企業や教育機関でも、マインドフルネスを取り入れたプログラムが導入されており、広く活用されています。
企業による支援事例:LAVAのメンタルヘルスプログラムとは
LAVAのメンタルヘルスプログラムではマインドフルネス(瞑想)を主軸にセミナー+ヨガ+マインドフルネス(瞑想)でプログラムが構成されています。マインドフルネスの実践により少しでも「今」という時間に意識をむけるだけで劇的にストレス改善効果が表れます。
LAVAプログラムの導入事例と成果

ここからは、実際にLAVAの法人サービスを導入された企業様のメンタルヘルス対策の取り組み事例をご紹介します。
・業界:システム開発
・課題:メンタルヘルス問題による休職者の増加
・内容:メンタルヘルスプログラム
・実施方法:オンライン配信
こちらの企業様ではメンタルヘルスに課題を抱え、休職や退職に至ってしまうケースが増えていることを課題とされており、日常的に実践できるマインドフルネスについてセミナーを実施させていただきました。
前半は座学でマインドフルネスによるストレス解消効果を解説し、具体的な実施方法をレクチャー、リラックスしていただけるようなゆったりしたポーズ構成のヨガを起こったあと、後半にはマインドフルネス(瞑想・呼吸法)を実施。
休日の午前中での実施ということもあり、参加者様はご自宅から集中した状態でご参加いただき、実施後のアンケートでも好評のお声をいただきました。
まとめ
・管理職は部下の管理やチーム運営に伴う課題解決を行い、仕事のプレッシャーや目標達成の要求等高い成果を求められることからストレスを抱えやすい。
・上司や経営陣からの期待と実際の業務にギャップがある場合、役割の不明確さや責任感の重さからストレスが生じる。
・仕事のプレッシャーを軽減するために、現実的な目標設定と業務の適切な分担が重要となり、部下の管理やチーム運営の課題に対処するために、リーダーシップ研修やコミュニケーションスキルの向上が必要。
管理職のメンタルヘルス対策を個々で取り組むものとせず、研修の導入やサポート体制を整え、企業として積極的に取り組み、企業全体の活性化へと繋げていきましょう。